医学部の解剖実習は大変?実習の忙しさや大変だったことについて解説
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:基礎知識
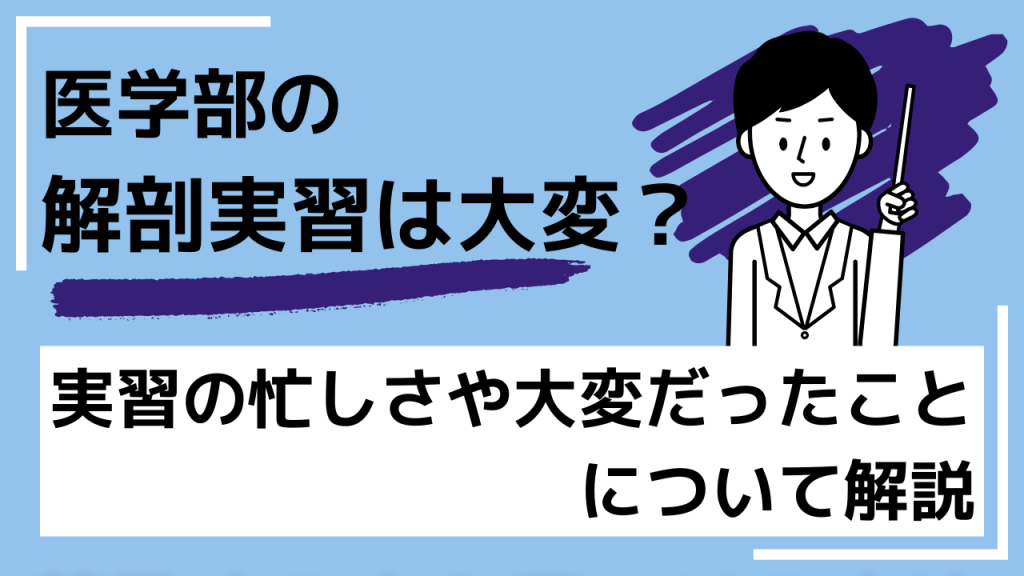
医学部の解剖実習は、医師になるための重要なステップであり、同時に大きな試練でもあります。
膨大な知識量や技術的な側面だけでなく、精神的な強さも試される厳しい実習です。
本記事では医学部の解剖実習の大変さや順序について詳しく解説しています。
記事内では医学部の解剖実習でよくある大変なエピソードや解剖実習で必要な持ち物についても解説をしているため、今後解剖実習を行う予定の方や医学部に入学したい方は是非参考にしてください。
解剖実習とは?
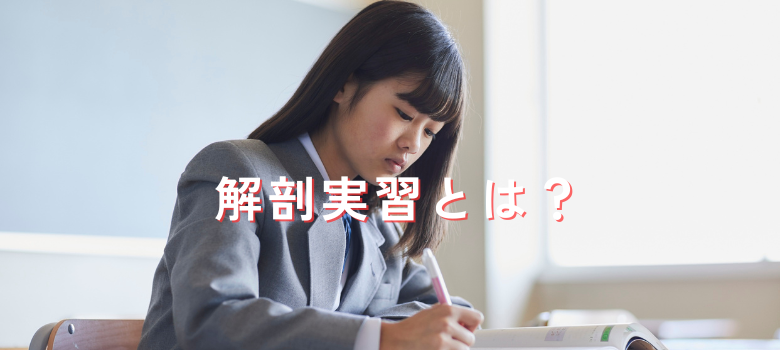
まずはじめに、解剖実習についてご説明します。
解剖実習とは、人体の構造を学ぶためにご遺体の解剖を行う実習のことです。
主に医学部医学科2年次に行います。
解剖実習では、実習所の手引きに従って全身を隅々まで解剖する「正常解剖」が行われ、学生数名で構成された1グループにつき1体のご遺体を数か月にかけて解剖します。
学生がより良い医師になるために、献体された大切なご遺体を解剖させていただくので、失礼がないよう丁重に扱うことが重要となります。
そのため、解剖実習は学生にとっても責任の大きい実習となります。
解剖実習の流れとは?
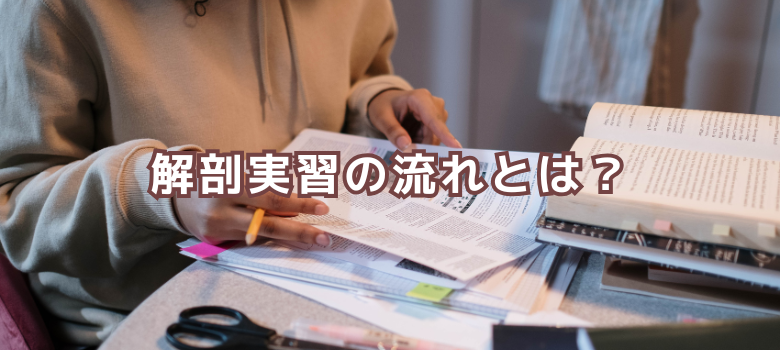
次に、解剖実習の流れについてご説明いたします。
班分け
解剖実習は、数人1組のグループで1つのご遺体を担当します。
班分けは、グループで協力し互いに助け合いながら実習を進めることによる協力体制の構築、意見交換を行うなどの知識の共有、コミュニケーション能力の向上などを目的としています。
ご献体と対面
解剖の自習室に踏み入れると、解剖台の上には白い布を被せた状態もしくはジッパーのような袋に入れられた状態でご献体が安置されています。
白い布を取り除いたとき、袋を開いたときにご献体と対面となります。
解剖
まずは表層の解剖を行います。
皮膚や脂肪組織などを丁寧に剥ぎ、深部の構造を露出させます。
次に深部の解剖を行います。
筋肉、神経、血管などを順に解剖し、それぞれの位置関係や構造を観察します。
解剖を進めながら、解剖書や図を参照し、観察した構造を記録します。
そのため、事前の予習がかなり重要となります。
男女の献体を見せ合う
実習ではグループごとにご遺体が1体と決まっているため、自分たちの担当するご遺体と異なる性別の解剖構造を確認することができません。
しかし、当然性別で体の構造が異なるため、両方の構造を確認する必要があります。
そこでグループごとに解剖実習で担当したご遺体の剖出部分を説明しあい、担当したご遺体とは異なる性別の構造についても知見を深め合います。
その中でも性器や胸部など性別によって大きく異なる箇所は、説明しあうことがとても大切になります。
休憩
解剖実習期間も、通常の授業と同様に昼食休憩も設けられています。
また、実習室内は飲食禁止のため、各自外出をして飲み物休憩やトイレ休憩などを取ることも可能です。
口頭試問
学んだ知識をどこまで理解しているのかの確認のため、解剖実習中に口頭試問が行われます。
解剖体の構造、機能、名称など幅広い範囲から問題が出されます。
解剖体を見ながら問題に答えますが、問題が出されたらすぐに答えなければなりません。
実習中に疑問に思った点は先生に質問をして理解を深めたり、事前に友人同士で問題を出し合うことにより口頭試問に慣れるなどの対策をしておくとよいです。
納棺
解剖実習終了後はご遺体を棺に納めます。
解剖後のご遺体はバラバラの状態のため、各臓器ごとに袋でひとまとめにするなど、出来る限り解剖が行われる前の状態に近づけて納めます。
また、担当させていただいたご遺体には、グループごとに花束を1つ献花します。
花束は事前に花屋で購入したもので、1,500円から3,000円くらいのものになります。
慰霊祭
最後に、医療の進歩・発展のためご献体された故人に対して感謝と敬意を表し、その魂を慰めるための儀式である「慰霊祭」を行います。
慰霊祭は、学びの場において人命の尊厳を再確認し、医療の倫理を学ぶ一環として行われることが一般的です。
慰霊祭は通常、大学や医療機関が主催し、献体された方々の遺族も招待されることがあります。
この儀式では、献体者への感謝の言葉を述べたり、お祈りを捧げたりすることが行われ、参加者が解剖学の学びの意義を再確認する機会ともなります。
慰霊祭に参加する際は、黒のスーツを着用し、染髪している人は黒に戻す必要があります。
解剖実習で必要なもの
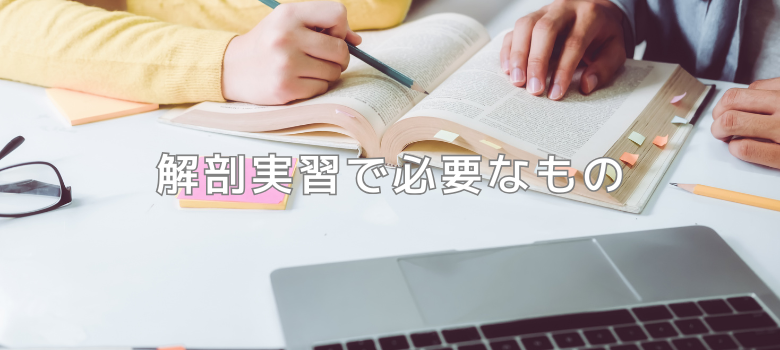
次に、解剖実習で必要なものについてご説明いたします。
解剖実習の手引き
まずは、解剖実習の手引きです。
解剖実習の手引きは解剖実習を行う際に参考となるガイドラインであり、実習を安全かつ効果的に進めるための指針となります。
手引きには、図による解剖構造の説明と解剖の手順が記載されています。
これは学生全員が持ち、予習するときなどにもこの手引きを参考に学びます。
実際に解剖中に見ながら学習もするため、汚れる可能性があります。
そのため、実習中に使用する手引きと家で予習するために使用する手引きの2種類を持っておくとよいでしょう。
参考書
解剖学の参考書は多くの出版社から様々なものが出版されています。
1つ目は解剖学アトラスです。
人体の構造を詳細な図で示したものです。
解剖実習中に、実際の標本と照らし合わせながら観察する際に役立ちます。
2つ目は解剖学テキストです。
各器官の構造や機能について詳細な解説がされています。
解剖学の基礎知識を深めるのに役立ちます。
参考書を選ぶ際には初心者向けのものや、中級者向け、上級者向けの参考書から、自分に合ったものを選ぶとよいでしょう。
解剖セット
解剖セットは解剖実習を安全かつ効率的に行うために不可欠なものです。
解剖セットには、メス、ピンセット、ハサミ、探針、その他道具(スケールやルーペなど)が含まれています。
解剖セットは大学協同組合(生協)、医療用品店、インターネット通販などで購入することができます。
解剖に必要な衣類
解剖に必要な衣類は主に5つあります。
1つ目は白衣です。
実習中は必ず使用します。
厚手のものが望ましく、汚れても問題ない素材を選びましょう。
2つ目は上履きです。
実習室で履き替える専用の靴です。
3つ目は長ズボンです。
汚れが付着しても問題がない長ズボンを着用しましょう。
4つ目は長袖です。
皮膚を露出させないように、長袖のものを着用しましょう。
綿素材など、通気性の良いものがおすすめです。
5つ目はエプロンです。
汚れから衣類を守るため防水性のあるエプロンを着用する必要があります。
このほかにも、帽子、眼鏡、タオルがあると便利です。
帽子は髪が長い場合は髪が顔にかからないように着用すると良いでしょう。
眼鏡は保護眼鏡があると、飛沫などが目に入るのを防ぎます。
タオルは手や汗を拭いたりするために用意しておくと便利です。
解剖実習があって大変だったこと
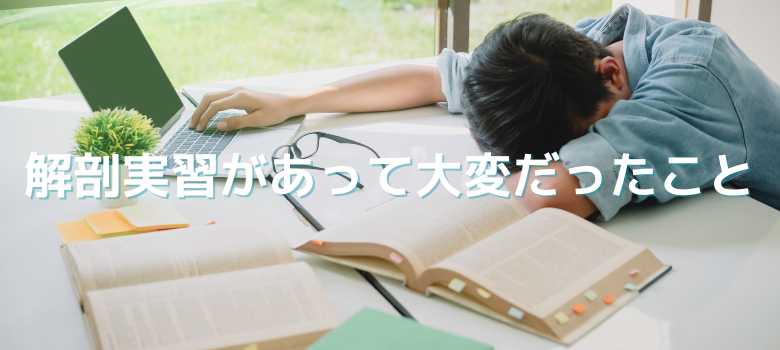
解剖実習は、一瞬たりとも気を抜かない状態が長時間に及び、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかるものです。
以下にて、解剖実習があって大変だったことについて説明いたします。
忙しくて時間が取れない
解剖実習は長時間立ちっぱなしで行われることが多く、体力を消耗します。
ピンセットやメスなどを使って細かい作業を行うため、集中力が必要です。
実習と同時に解剖学の知識を習得する必要もあり、時間的な余裕がなくなることがあります。
実習後にはレポートを作成する必要があり、解剖実習以外にも他の科目を並行して行う必要があるため、時間管理が難しい場合があります。
においがきつい
ホルマリンなどの防腐剤の強い刺激臭や、ご献体から発せられる特有の臭いは、想像を絶するほど強烈で、長時間作業を行う上で大きな負担となります。
また、解剖に使用する薬品や、その他処理に使用される薬品の臭いも、臭いがきついと思われる原因となっています。
中には倒れる人も?
解剖実習で倒れてしまう人は決して少なくありません。
人間の体を解剖するという経験は多くの学生にとって初めてのことで、緊張や恐怖から自律神経が乱れ、気分が悪くなることがあります。
またホルマリンの強い刺激臭が呼吸器を刺激し、めまいや吐き気を起こしたりすることもあります。
気分が悪くなった場合はすぐに周囲の学生や先生に助けを求め、倒れてしまった場合は無理せずに休憩を取りましょう。
実習前に体調不良を感じている場合は、事前に教員に伝えておくとよいでしょう。
カビが発生してしまう
解剖体は、乾燥による組織の硬化と防腐のためアルコールやホルマリンで処置され、湿潤な状態が保たれるため、カビが発生しやすくなっています。
特に解剖体の保存と管理が地下で行われている場合や、6月や7月など高温多湿な時期の解剖実習では、カビの発生に気を付ける必要があります。
カビは拡散性が高いため、一度カビが発生してしまうと数日で蔓延し、制圧が困難になるほか、実習の進行に影響が出てしまい、モチベーションの低下にも繋がります。
対策としては最初のカビの発生をさせないことと、もしカビを発見した場合はすぐに対処することが挙げられます。
スクランブルエッグが食べられなくなる
皮下脂肪は半熟のスクランブルエッグに似ているため、スクランブルエッグが食べられなくなったという人や、焼肉も筋肉や内臓そのものに見えて食べたくないという意見もありました。
しかし、実習前にそういった噂は聞いていたけれど、実際に周りでなっている人はいなかったという声もあるので、意識しすぎるとそうなってしまうのかもしれません。
まとめ

この記事では、医学部の解剖実習について、実習の流れや注意点などを解説しました。
解剖実習は技術面だけでなく精神面も鍛えられる厳しい実習です。
入学する前は医学部がどのような実習を行っているのか、イメージがつきにくいかと思います。
医学部を志望している受験生の方はぜひこの記事を参考にしてみてください。
この記事の執筆者:医進の会代表 谷本秀樹

大学入試は四谷学院などの大手予備校や多くの医学部受験予備校で、主に生物の集団授業と個別授業で300人以上の受験生を担当。
自身の予備校『医進の会』発足後は、これまで500人以上の生徒の受験と進路指導に携わってきた。
『個別の会』の代表でもあり、圧倒的な医学部入試情報量と経験値、最適なアドバイスで数多くの受験生を医学部合格に導いてきた、医学部予備校界屈指のカリスマ塾長。

