医学部のいじめやハラスメントとは?原因や事例、対策なども解説
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:基礎知識
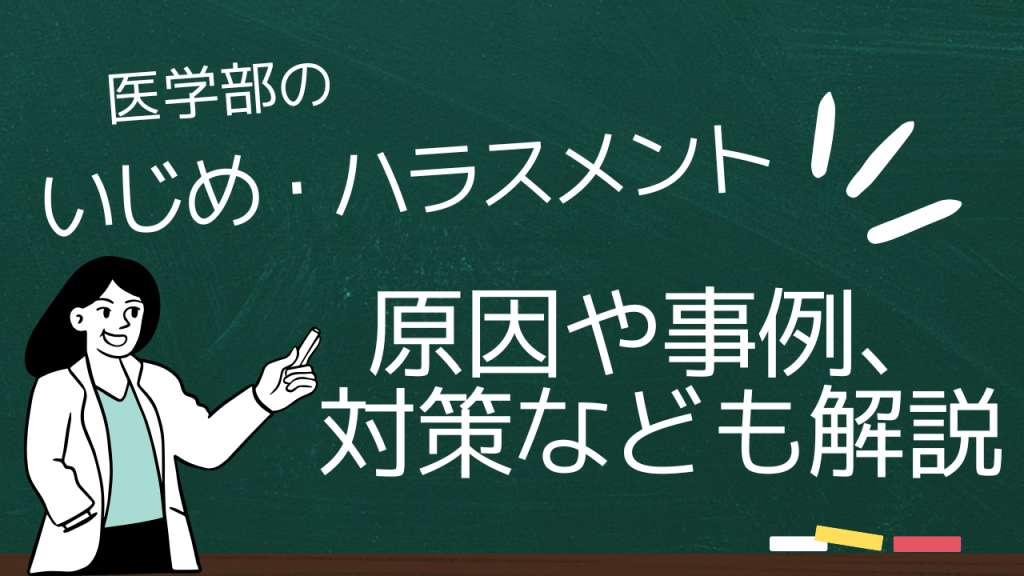
医学部で、時にいじめやハラスメントが起こることがあるのをご存知でしょうか。
このコラムでは、いじめ・ハラスメントがどのようなときに起こりうるのかをその形態や原因、事例などを用いてお伝えします。
そして、いじめが耐えられないときの対処方法や具体的な対策も解説するので、ご参考ください。
医学部のいじめやハラスメントとは

まずは、医学部特有のいじめやハラスメントにどのようなものがあるのかをご紹介します。
医学部特有のいじめやハラスメント形態
医学部ではさまざまな形態のいじめ・ハラスメントが存在しています。
アカデミックハラスメント
医学部生ならではのハラスメントの一つが、アカデミックハラスメントです。
アカデミックハラスメントとは、教授など教育や研究上で優位な立場にあるとされる人が教育や研究、さらには就学において不利益を与える言動を指します。
事例としては論文を添削する際に暴言を吐かれる、単位を与えない、文献を使わせないなどがあります。
ジェンダーハラスメント
女性医学生へのジェンダーハラスメントは、性別に基づく差別的発言や固定観念に起因するものが多く見られます。
例えば、「女性には外科は向かない」などの発言が、学生の自己肯定感を損ない、将来のキャリア選択に悪影響を与えることがあります。
大学側は、こうした発言を防ぐために教職員や学生への意識改革を目的とした研修や啓発活動を行い、ジェンダー平等な環境の整備を進めています。
医学部でいじめが起こる原因とは

次に医学部でいじめが起こる原因についてまとめてみました。
人間関係
医学部でいじめが起こる背景には、人間関係における上下関係の厳しさや、患者の生命を扱う特有の緊張感によるストレスが関与しています。
医学部では、学年や役職による上下関係が厳格で、後輩や部下に過度な指導を強いる風潮が根強い場合があります。
このような環境では、指導が行き過ぎていじめに発展するケースが見られます。
さらに、医学の学習や臨床実習では、患者の命に直結する判断が求められる場面が多く、学生や医療従事者に強い精神的ストレスを与えます。
このストレスが人間関係悪化や感情の爆発につながり、いじめの温床となることがあります。
上下関係の改善やメンタルケアの充実をさせることでこれらの問題を解決させることができます。
長時間労働や過酷な勉強環境
長時間労働や過酷な勉強環境による疲労やストレスは、人間関係の構築を難しくし、いじめを引き起こす土壌を作りだすこともあります。
その理由として、学生同士が十分にコミュニケーションの時間を取れない状況が続くことで相互理解を深める機会を奪われ、誤解や対立を生むきっかけになるからです。
また、周囲との関係が希薄になることで、孤独感を抱く学生も少なくありません。
孤独感はいじめられやすい状況を作り出す可能性があります。
このように、医学部の長期間労働や過酷な勉強環境は、学生たちの心身に大きな負担をかけ、深刻な問題となっています。
医学部生活で起こりやすいいじめの事例
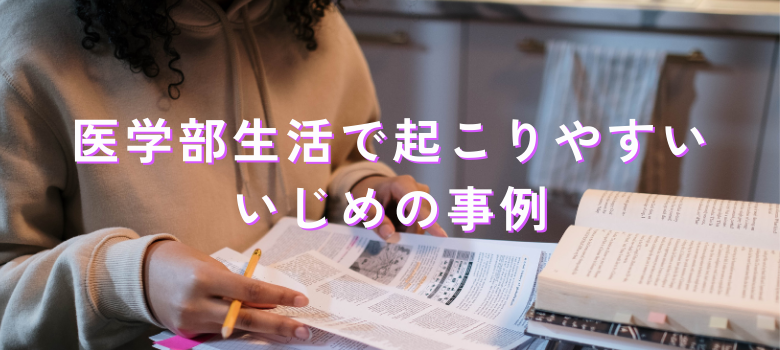
次に、医学部生活で起こりやすいいじめの事例について解説します。
留年生に対するいじめ
進級できた学生と留年生との間には軋轢が発生しやすくなり、その軋轢がいじめにつながります。
軋轢が発生する理由として、学力差による優越感および劣等感が生じるからです。
進級できた学生は、ある程度の学力があることを証明しており、それが優越感につながることがあります。
一方、留年生は学力に自信が持てず、劣等感を抱きがちです。
そういった感情差から軋轢が発生しやすくなり、周囲の学生や教員が、留年生に対して無意識のうちに差別的な態度をとってしまうことがあります。
進級できた学生と留年生では、1年分の差があり、その差が心理的な距離を生んでしまいます。
また、留年生は卒業が遅れることによる将来への不安、ストレスを抱えがちです。
その不安、ストレスが周囲への攻撃性や孤独感につながり、いじめのきっかけとなってしまいます。
いじめを受けた留年生は、学習意欲を失い、さらに成績が伸び悩んでしまう悪循環に陥る可能性もあるので、留年生に対して偏見をもたずに公平な態度を取ることが重要です。
また、留年生は不安やストレスを抱え込まないように注意しましょう。
臨床実習中のいじめ
臨床実習という貴重な経験の場でも、いじめが多く発生しています。
パワーバランスの不均等により、上級医や研修医、先輩医学生、看護師などの経験や知識が豊富な者からのいじめが多く見られます。
具体的には、過度な叱責や質問への無視、医療に関する専門用語や知識を利用して精神的に追い込むような行為が見られます。
ひどい場合、患者さんの前でわざと失敗させたり、悪口を言ったりなど、患者さんを巻き込むような行為も見られます。
また、医療現場は忙しいということもあり、十分なコミュニケーションが取れないことで人間関係がギクシャクし、いじめが発生することもあります。
医療現場という閉鎖的な環境は、いじめが外部に知られにくいという特徴があります。
いじめが発生した場合、1人で抱え込まず、先生や友達、家族など、身近な人にすぐに相談をしましょう。
医学部生のいじめ対策やサポート
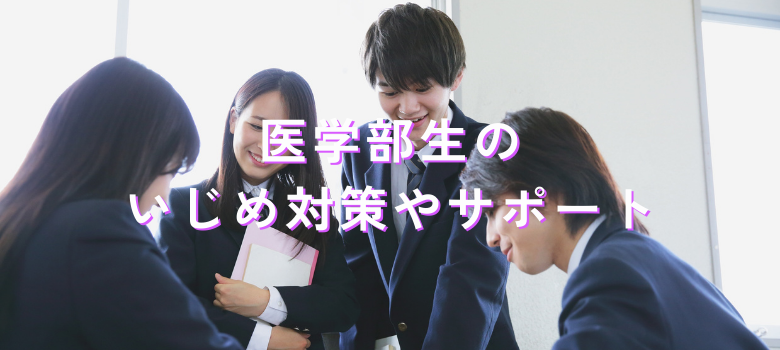
次に医学部生のいじめ対策やサポートについてまとめてみました。
大学側の取り組み
医学部でいじめが発生した場合、大学側はその状況に適切に対応するために、いくつかのサポート体制を整えることが求められます。
いじめが疑われる場合、大学はその事実関係を調査します。
この調査は、公正かつ迅速に行われるべきです。
いじめの加害者とされる学生に対しては、面談や警告、指導が行われることがあります。
医学部のように特に厳しい学業環境において、いじめ問題が深刻化する前に、大学が積極的に問題を把握し、適切に対処することが大切です。
ハラスメント相談窓口の設置
多くの大学では、学生がいじめの問題について匿名で相談できる窓口を設けています。
例えば、学生支援センター、カウンセリングセンター、学生相談室などがそれにあたります。
ここでは、専門のカウンセラーや相談員が対応し、被害を受けている学生の心情や状況に寄り添いながら解決に向けたサポートを行います。
教職員向けハラスメント防止研修の実施
教職員向けのハラスメント防止研修では、まず、ハラスメントについて正しく理解をします。
そして、気づいていないハラスメント発言・行為について学校という環境下での行動を改善するため解説し、教員の行動を変革します。
グループワークも実施されており、学校での人間関係を意識した上での注意の仕方や褒め方について意見を共有します。
学生自身でできる対策
学生は日頃からいじめを意識する必要があります。
また、学生自身が対策をすることによってより多くのいじめを防ぐことができます。
信頼できる仲間づくりやストレス管理、自己肯定感の維持などがありますので、紹介します。
信頼できる仲間づくり
いじめに対処するためには、信頼できる仲間づくりが非常に重要です。
信頼できる仲間がいれば、心の支えになるだけでなく、いじめの問題を共有し、協力して解決に向かうことができます。
自分自身を大切にし、共通の関心や価値観を持った人々と誠実に関わることで、強固な信頼関係を築くことができます。
その結果、心の支えとなり、困難を乗り越える力となるでしょう。
ストレス管理と自己肯定感の維持
自分自身をまずは自分が認め、自己肯定感とともに相手を大切に思う気持ちを常に持っておきましょう。
家庭内で役割を持ってみると、自己肯定感に繋がるため、おすすめです。
また、ストレス管理として、学生は栄養の取れた食事や睡眠など生活リズムを整えることも重要です。
医学部でのいじめが耐えられないときの対処方法
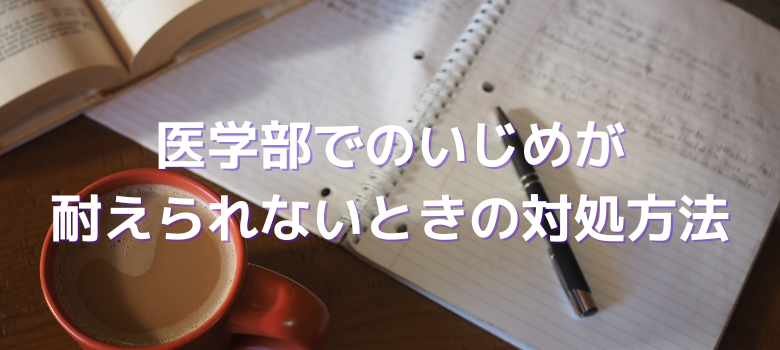
続いて、医学部でのいじめが耐えられない時の対処法についてご紹介します。
いじめの実態を把握する
まずはいじめの実態を正確に把握する必要があります。
そのため、医学部特有のいじめパターンを理解しておきましょう。
また、ハラスメントにも種類がありその種類と頻度を認識しておきましょう。
そして、いじめの証拠は保存・記録しておき、真実を伝えられるようにしておくことでいじめの実態を第三者目線でも把握することができます。
さらに、被害者は加害者と距離を置くことで自分を守れるようにしておくとよいです。
専門家のカウンセリングを受ける
専門家のカウンセリングを受けることも重要です。
いじめの被害者は声を上げづらい状況にあります。
そこで遠すぎず近すぎない距離感の専門家のカウンセリングであれば、自分の事も話しやすく相談しやすいと考えられます。
また、自分の気持ちを打ち明けることで少しでも気持ちが楽になれる可能性があります。
転科や転学を検討する
いじめの状況に耐えられなくなった場合は、転科や転学を検討してみましょう。
いじめが解決されても、その相手が同じ空間にいることがストレスとなる場合もあります。
そのため、無理にその場所に留まろうとせずに、転科や転学で自ら環境を変えることも可能です。
まとめ
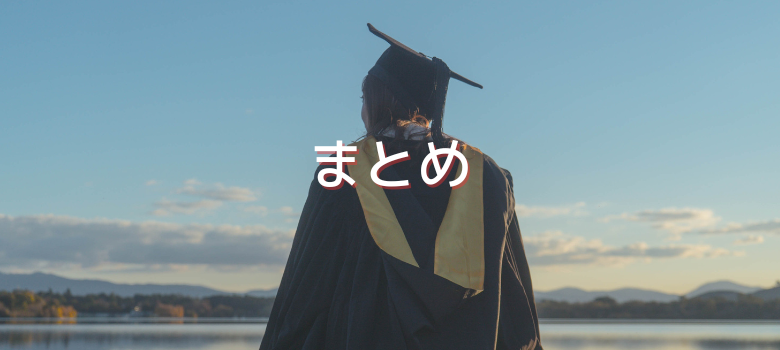
今回は、医学部のいじめについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
いじめを防ぐには、まずは全員がいじめはしてはいけないという意識を持つとともに、自分を大切にし相手を思いやることが必要です。
いじめは起きないことが一番ですが、もし何か辛いことがあれば、はやめに勇気を出して誰でも良いので相談してみましょう。
この記事の執筆者:医進の会代表 谷本秀樹

中学入試の希学園の集団授業で600名以上の多くの生徒を受験指導。
大学入試は四谷学院などの大手予備校や多くの医学部受験予備校で、主に生物の集団授業と個別授業で300人以上の受験生を担当。
自身の予備校『医進の会』発足後は、これまで500人以上の生徒の受験と進路指導に携わってきた。
『個別の会』の代表でもあり、圧倒的な医学部入試情報量と経験値、最適なアドバイスで数多くの受験生を医学部合格に導いてきた、医学部予備校界屈指のカリスマ塾長。

