医学部の推薦入試が「ずるい」と言われる理由!メリットやデメリット、試験対策のポイント
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:入試
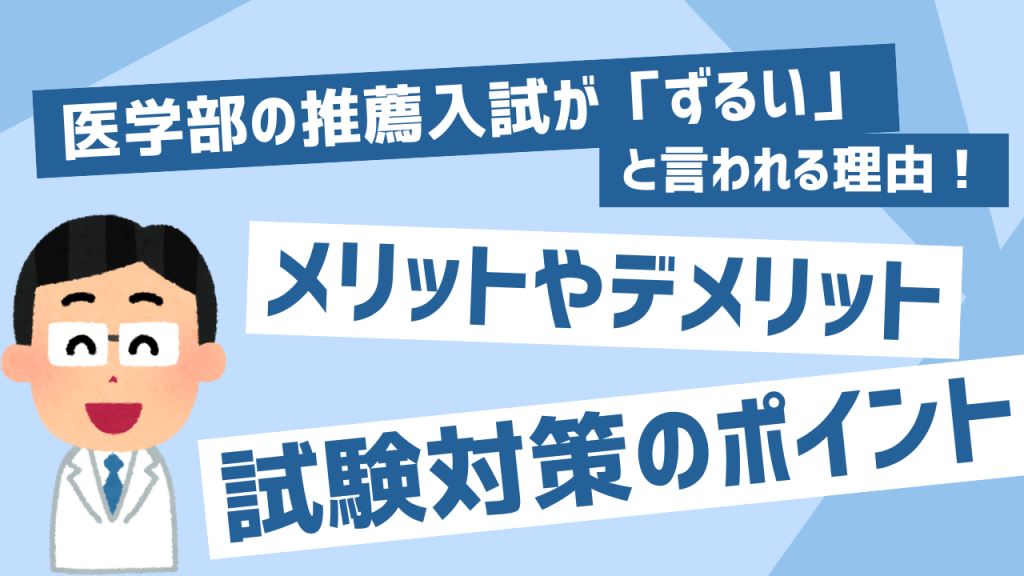
医学部受験は競争率が高く最難関と言われています。
このコラムでは、推薦入試が「ずるい」と言われる理由や、逆に「ずるくない」と言われる理由について詳しく解説しています。
医学部受験や、推薦入試にご興味のある方はぜひ参考にしてください。
医学部の推薦入試が「ずるい」と言われる理由
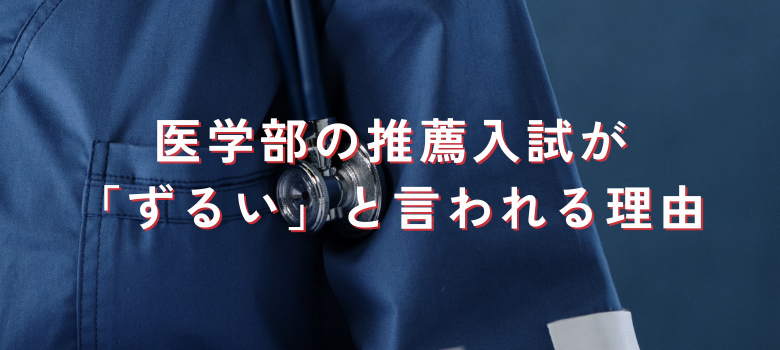
はじめに、医学部の推薦入試が「ずるい」と言われる理由についてまとめました。
学力・偏差値が低くても合格の可能性があるから
一つ目は、学力や偏差値が低くても合格の可能性があるからです。
医学部の一般入試で合格するためには、共通テストだけでなく、問題レベルが高い二次試験を突破しなければいけません。
推薦入試は、このような二次試験を受けなくて良い場合があるので、「ずるい」と思われることがあります。
推薦入試では面接や小論文が課されるため、勉強しなくても楽に合格できるというわけではありませんが、一般入試よりも共通テストで足切りされる点数が低いところもあり、一般受験に比較して学力や偏差値が低くても合格できる可能性は高いといえるでしょう。
高校3年間の評定や課外活動が重視されるから
二つ目は、高校3年間の評定や課外活動が重視されるからです。
推薦入試では、人柄が重視されます。
具体的には、高校3年間の評定とボランティアへの参加や学校行事への取り組み方、または部活動や課外活動でどのような結果を残しているかが評価の対象となります。
推薦の出願には評定4.5以上などの条件があることがほとんどで、ある程度学校の成績が優秀でないと出願できませんが、このように、共通テストや二次試験のような入試時の学力成績とは別の部分で評価が行われることに対して「ずるい」と感じる方もいるようです。
地域枠による出願者を限定しているから
三つ目は、地域枠による出願者を限定しているからです。
地域枠推薦では、出願条件で住んでいる地域が限定されていることがほとんどです。
卒業後にその地域で指定の期間就労することを条件に全国から募集可能な大学もありますが、多くの大学の地域枠推薦では地元の学生にしか受験資格がないため、生まれた地域という自分では変える事ができない要素が影響することに不公平さを感じて不満を抱く方もいるようです。
医学部の推薦入試が「ずるくない」と言われる理由
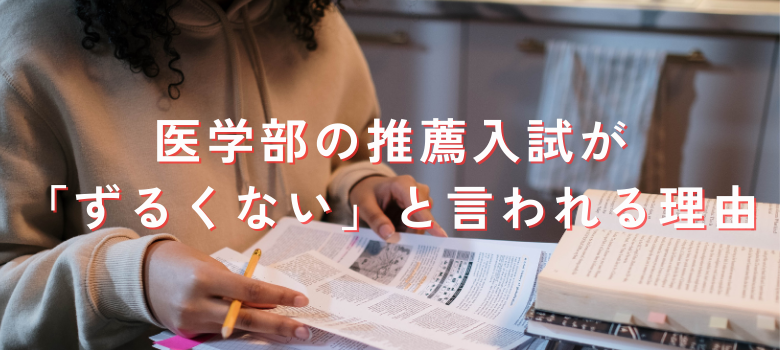
次に医学部の推薦入試が「ずるくない」と言われる理由についてまとめました。
面接と小論文による総合的な能力評価がされるから
一つ目は、面接と小論文による総合的な能力評価がされるからです。
偏差値として求められる学力レベルが一般入試と比較して低いとしても、面接や小論文では筆記テストでは測ることができない能力が求められるからです。
例えば、面接ではコミュニケーション能力や自分の意見を適切に相手に伝える能力などが必要となります。
小論文では論理的思考力や読解力、自分の考えを整理して伝える表現力が必要となります。
そのため、推薦入試は学力だけではなく、能力が総合的に判断される入試であるといえます。
推薦入試は誰にでも平等にチャンスがあるから
二つ目は、推薦入試は誰にでも平等にチャンスがあるからです。
地域枠推薦の場合はやや異なりますが、基本的に推薦入試は高校3年間の評定が一定のレベルを超えていて、出願条件を満たしていれば、誰でも応募することが可能です。
推薦入試がずるいと思っている人のなかには、評定が足りずに応募ができなかった方もいるかもしれません。
1、2年生から定期テストを真面目に頑張って、校内活動や課外活動で努力をする機会は平等に与えられているので、推薦入試はずるくないといえます。
医療従事者としての適性が重視されるから
三つ目は、医療従事者としての適性が重視されるからです。
推薦入試では、面接や小論文を通して能力を総合的に判断し、将来医療従事者として働く上での適性を重視して評価されます。
そのため、大学が求めている医療従事者の人物像に、よりマッチしている受験生が合格に近づくこととなります。
一般入試とは違う評価軸で比較され判断されることになりますが、どの受験方式においても判断は公平であるといえるでしょう。
医学部の推薦入試のメリット
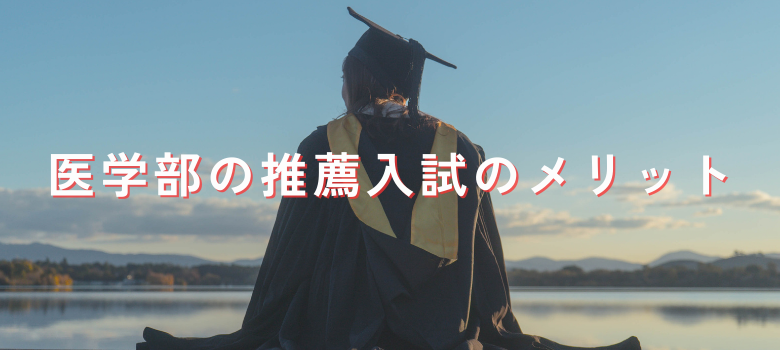
次に、医学部の推薦入試のメリットについてまとめました。
試験科目数の減少で負担が軽減される
一つ目は、試験科目の減少で負担が軽減されることです。
推薦入試では一般入試に比べて、試験科目や出題範囲が少なく、難易度が易しい場合があります。
そのため、一般入試よりも必要な学習量が少なく、受験生の負担が軽減されます。
一方で、面接や小論文など学力テス
トとは別で試験がありますので、推薦入試に特化した受験対策は必須となります。
また、一般入試のように高いレベルの問題が出題される二次試験はありませんが、大学によっては共通テストが課される場合や共通テストの点数で足切りがある場合もあるので、最低限の学力レベルは必要となります。
現役生・1浪生に有利な条件が設定されている
二つ目は、現役生・1浪生に有利な条件が設定されていることです。
出願条件を満たしている場合、受験の機会を増やし、医学部合格に近づくことができます。
多くの出願条件としては、現役生・1浪生までなどとなっているため、倍率を下げることができます。
地域枠による定員増加の可能性がある
三つ目は、地域枠による定員増加の可能性がある場合です。
地域の医師を確保するため、地域枠という入試区分が学校推薦型や総合型選抜に設けられています。
出願資格である地元出身の方という条件を満たしている場合、医学部合格の機会を増やすことができます。
学習成績不問の大学の存在
四つ目は、学習成績不問の大学があるということです。
学校推薦型や総合型選抜では、一定以上の成績が必要です。
しかし、大学によってはその成績による条件が不問の場合もあります。
定期的に情報収集を行っておきましょう。
医学部の推薦入試のデメリット
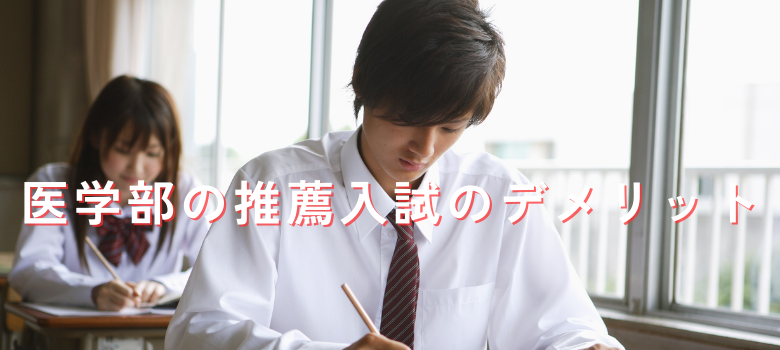
ここまで医学部推薦入試のメリットについてお話ししました。
次は、医学部の推薦入試のデメリットについてご紹介します。
地域枠は卒業後の勤務地が制限される
地域枠入試で入学した学生は、一般的に卒業後に特定の地域で一定期間働くことが義務づけられます。
この義務期間は地域によって異なりますが、通常は数年(例えば、3〜10年程度)と定められており、その間は指定された地域の医療機関で働かなければならない場合があります。
このため、卒業後に自分の希望する場所や専門分野で働きたいという場合でも、地域枠の制約によってその希望が叶わないことがあります。
特に都市部で働きたい場合や、特定の病院・医療機関で働くことを望んでいる場合、地域枠入試に進むとその選択肢が制限される可能性があります。
将来のキャリアパスに影響がある
推薦入試で合格した学生は、特定の学校やコースに進むことが前提となります。
そのため、将来の専門分野や進路選択の幅が狭くなる可能性があります。
特に、推薦入試がある特定の条件や目的に基づいて選ばれている場合、選択肢が制限されてしまうことがあります。
また、推薦入試では、志望動機や人物評価が重要視されるため、最初に入学時に自分が本当に望んでいる分野やキャリアに適していない場合、学業や臨床実習が思うように進まないことがあります。
将来的には、自分の興味や能力に合った分野に進むことが難しくなる可能性もあります。
一般入試と比較した際の学力差への不安が残る
一般入試で選ばれた受験生は、相当な時間を勉強に費やしてきている為、推薦で入学した受験生たちとは学力差があります。
推薦入試の合格発表は、はやくて年内となっています。
そのため、大学入学までの期間を勉強しなければ、大学入学後に授業についていくのが難しくなります。
また、推薦入試で選ばれた学生は、他の受験方法と比べて学力や知識が必ずしも高くない場合があり、医学部で必要とされる基礎的な学力が不足していると、後々その差が顕著になることがあります。
推薦入試対策のポイント

次に、推薦入試対策のポイントについて解説します。
志望動機を適切に作成する
推薦入試では、志望動機が合否を大きく左右する重要な要素となります。
ただ単に、「その大学に行きたい」と書くのではなく、なぜその大学・学部なのか、具体的に説得力を持って伝える必要があります。
志望動機を作成する上で、大学のアドミッション・ポリシー(入学者選抜)の関係性は非常に重要です。
大学はただ単に成績が良い学生だけでなく、その大学の教育理念に共感し、将来に活躍できる人材を求めています。
志望動機で、その人物像に合致していることを示すことで、選考委員に強い印象を与えることができます。
また、志望動機では、具体的な経験や目標と結び付けて、説得力のある文章を作成することが大切です。
部活動、ボランティア活動、留学経験など、これまでの経験を具体的に書き、経験を通して学んだことや感じたこと、得られた気づきなどを具体的に記述しましょう。
自分の経験から医師としての適性をアピールするのも良いでしょう。
そして、将来の目標を明確にしておくことも重要です。
将来、どんな医師になりたいのか、なぜその目標を持ち、それを達成したいのか、自分の将来像を描いておきましょう。
自分の経験や目標を伝えれば、経験や目標と志望動機を結び付け、なぜその大学・学部で学びたいのかを説明しましょう。
面接・小論文対策を綿密に行う
医学部では、高い学力だけではなく、患者と向き合う上で必要な人間性、倫理観といった人物としての側面も重視されます。
推薦入試の面接や小論文では、これらの要素を測る重要な機会となるため、綿密に対策を行う必要があります。
面接・小論文対策において、コミュニケーション能力と論理的思考力の向上は合格に不可欠な要素です。
コミュニケーション能力を向上させるために、家族や友人との会話の中で、自分の意見を相手にわかりやすく伝える練習をしましょう。
また、相手の話をじっくり聞き、共感する力を養うことも大事です。
自分の表現や声のトーンに注意することで相手に好印象を与えることもできます。
また、小論文では論理的な思考力と表現力が求められます。
社会問題や医療問題に関する記事を読み、自分の意見をまとめる練習をしたり、医学書だけでなく幅広いジャンルの本を読むことで思考力を養いましょう。
また、友人と議論を行い、自分の意見を論理的に説明する練習をしたり、塾の先生や学校の先生に添削をお願いし、文章の構成や表現力を改善する機会を作ることも重要です。
自己の適性と将来のキャリアプランを慎重に検討する
推薦入試では、学力だけではなく自身の個性や熱意が評価されます。
その中でも、自己の適性と将来のキャリアプランは、面接や小論文で必ず問われる重要な要素で、慎重に検討する必要があります。
まず、自己の適性を知るために、自己分析を行いましょう。
どんなことに興味があり、なぜその分野を学びたいのかを明確にし、どんなことを大切にして生きているのか、自分の価値観を整理しましょう。
また、自分の強みを活かし、弱みを克服するためにどういった努力をしてきたのかを具体的に説明できるようにしておきましょう。
将来のキャリアプランを具体的に描くためには、大学で学びたいことや将来どんな仕事に就きたいのか、目標を考えてみることが大事です。
そして、なぜその目標を持ち、それを達成したいのか、社会にどのように貢献したいのか、自分の未来像を描きましょう。
出願条件と大学の特色を徹底的に調査する
推薦入試では、出願条件と大学の特色をしっかり把握しておくことも重要です。
出願条件は大学や学部ごとに異なるため、個別に細かく確認する必要があります。
また、年ごとに変更される場合もあるため、過去の入試情報を調べて、過去の出願条件や試験内容を知ることで、より実践的な対策が立てやすくなるでしょう。
大学の特色は志望動機や自己PRを効果的に作成するために重要であり、自分がその大学で学びたい理由や大学の理念に合った人物像を示すことで、強いアピールをすることができます。
大学の公式ホームページは、最も信頼性が高く、最新の情報が得られます。
大学の理念・教育方針、学部・学科の特徴、特色あるプログラムや研究活動などに注目して情報を収集するとよいでしょう。
また、学内イベントやオープンキャンパスに参加することもおすすめです。
実際に参加することで、大学の雰囲気や教育内容を体感することができたり、入試担当者や教授と直接話す機会がある場合もあるため、具体的な質問をすることで、より深く理解することができるでしょう。
一般入試との併願戦略の立案
一般入試と併願する場合は、それぞれの入試の特徴を理解し、最も有利な結果を得るための戦略を考えることが重要です。
併願のメリットは、一つの入試方法に依存するのではなく、両方を受けることで不安を減らせたり、推薦入試で合格すれば一般入試の準備に時間をかける必要がなくなることです。
また、推薦入試で結果が振るわなかった場合でも、一般入試の準備を引き続き行うことができます。
併願戦略としては、まず推薦入試に全力を尽くし、万が一不合格だった場合に備えて、一般入試の準備も並行して行うことが基本的な方針となります。
推薦入試の合格発表後に一般入試の準備を始めるのは遅いため、予備期間を早めに設けておくことも重要です。
推薦入試の試験日や発表日を確認し、それに合わせて一般入試の勉強計画を調整しましょう。
そして、両方の入試に合格する可能性を最大化するために、メンタル面のケアや準備の段取りをしっかりと行いましょう。
まとめ

今回は、医学部の推薦入試が「ずるい」と言われる理由や、推薦入試のメリット・デメリット、試験対策のポイントなどについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
医学部の推薦入試は学力だけでなく、人間性や社会貢献活動が重要な評価ポイントとなります。
面接や小論文に向けた準備をしっかり行い、医療に対する情熱や医師としての適性をアピールすることがカギとなります。
また、一般入試に向けた準備も並行することでリスクを分散させつつ、万全の態勢で推薦入試に臨むとよいでしょう。
この記事の執筆者:医進の会代表 谷本秀樹

大学入試は四谷学院などの大手予備校や多くの医学部受験予備校で、主に生物の集団授業と個別授業で300人以上の受験生を担当。
自身の予備校『医進の会』発足後は、これまで500人以上の生徒の受験と進路指導に携わってきた。
『個別の会』の代表でもあり、圧倒的な医学部入試情報量と経験値、最適なアドバイスで数多くの受験生を医学部合格に導いてきた、医学部予備校界屈指のカリスマ塾長。

