北海道大学医学部のレベルは?偏差値や共通テスト得点率について徹底解説
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:大学情報

北海道大学医学部は北海道札幌市にある国立大学です。
本記事では北海道大学医学部の基本情報や倍率、偏差値等について詳しく解説しています。
北海道大学医学部への受験を考えている方や医学部に興味のある方は是非本記事を参考にしてみてください。
北海道大学とは?

北海道大学の基本情報についてご紹介いたします。
教育について
未来のリーダーを育てることを目指し、既存の概念や価値観にとらわれることなく、新しいアプローチで知識を広め、革新的なアイデアを育成することを重視しています。
この目標達成のために、フロンティア精神、国際性の向上、全人教育、そして実学の重要性という4つのビジョンを掲げています。
また、2011年からは学部別の入試制度に加えて、総合入試と言われる新たな入試制度を導入しています。
総合入試では、まず文系や理系の総合入試に応募し、志望と1年次の成績に基づいて学部や学科に移行できるシステムがとられています。
1年間は全学生が総合教育部で、広範な教養科目や基礎科目を学ぶことになり、学部に移行する前に進学先をじっくり考えることができます。
施設・設備について
札幌キャンパスには、クラーク会館、インフォメーションセンター「エルムの森」、総合博物館、中央食堂、生協会館等が備えられています。
これらの施設は、学生の日常生活をサポートするために、食事や書籍、文房具などの提供を行っています。
同様に、函館キャンパスにも学生食堂や売店があります。
クラーク会館は北海道大学創立80周年を記念して1960年に建設された大規模な学生館であり、サークル集会室や、キャリアセンターも併設されています。
さらに、福利厚生施設の一環として、生協会館の1階では食品や生活必需品の販売がされており、2階の書類部では教科書や新刊書などが充実しています。
キャンパスについて
| 学部 | 所在地 |
|---|---|
| 文学部 | 北海道札幌市北区北10条西7丁目 |
| 教育学部 | 北海道札幌市北区北11条西7丁目 |
| 法学部・経済学部 | 北海道札幌市北区北9条西7丁目 |
| 理学部 | 北海道札幌市北区北10条西8丁目 |
| 医学部医学科 | 北海道札幌市北区北15条西7丁目 |
| 医学部保健学科 | 北海道札幌市北区北12条西5丁目 |
| 歯学部 | 北海道札幌市北区北13条西7丁目 |
| 薬学部 | 北海道札幌市北区北12条西6丁目 |
| 工学部 | 北海道札幌市北区北13条西8丁目 |
| 農学部 | 北海道札幌市北区北9条西9丁目 |
| 獣医学部 | 北海道札幌市北区北18条西9丁目 |
| 水産学部 | 北海道函館市港町3丁目1の1 |
文学部~獣医学部までは札幌キャンパス、水産学部のみ函館キャンパスです。
コースについて
医学部の卒業までの4つのコースについてまとめました。
医学教養コース
入学後の最初の一年間は、総合教育部で学びます。
他の理系学部の学生とともに様々な教養科目を学ぶことで、広い視野や豊かな人間性を築くことが期待されます。
これは、人間性を向上させ、生涯医者としての基盤を築くために重要な時期です。
医学以外の文系科目や、理系科目に取り組むことは、一見医学とは関係のないように見えても、これが後の医学研究や医療の現場での創造性や発想力、広い視野を形成する原動力となります。
基礎医学コース
このコースは2年次の1学期から3年次の1学期まで、合計1年半にわたります。
最初に人体の正常な構造と機能について学習します。
それに加えて、生命現象を分子・遺伝子レベルで理解します。
同時に正常から病気に至るまでの基本的なプロセスについても学びます。
さらに、人間の健康と病気についてあらゆる視点から、社会医学系の科目も学びます。
これには、人間集団相互作用、環境問題、社会制度、予防等が含まれます。
なおこのコースから始まる医学の専門科目は全科目が必修であり時間割も濃密になっています。
臨床医学コース
このコースでは、様々な疾病について学びます。
臨床医学の基本である内科学、外科学、専門医学などを包括的に理解します。
患者を感情豊かな人間として理解し、その病態や診断、治療の基本を身につけます。
これは次の段階にある「臨床実習」に進むうえで非常に重要なステップです。
このコースでは、医学研究の基本となる医学研究演習が1カ月行われます。
学生は研究室に参加し、実験の手法や思考方法を学ぶことで、将来の基礎医学研究者や研究医としての資質を養います。
最後にはコンピューターによる知識や理解度を評価するCBT、さらに医療面接や診察などのスキルを測定する実技試験「臨床実習前OSCE」といった2つの全国共通の共通試験があり、これに合格することで臨床実習に進むことが出来ます。
臨床実習コース
このコースでは臨床実習が始まります。
4年次後半からは、北大病院で様々な診療科を経験し、病院で患者や、医療スタッフと交流しながら、これまでに各コースで学んできた知識を具体化し実践的な形で磨いていきます。
この実習と同時に実習で見つけた課題や疑問について、臨床統合講義で振り返り、広範で総合的な診療スキルを深めます。
社会医学の実習もこの時期に行います。
5年次の後半には、大学病院や外部の医療機関で4週間にわたる長期のコア科型臨床実習を行います。
6年次の前半では1つの診療科や教室ごとに4週間にわたる長期の選択型臨床実習を3回行います。
このコースの終盤には卒業試験のうちの一つとして全国共通の共用試験「臨床実習後OSCE」が行われ、臨床スキルと態度が評価されます。
その後に行われる医師国家資格に合格すれば医師としての資格を取得できます。
北海道大学医学部のレベルは?

北海道大学医学部の偏差値や倍率についてまとめました。
偏差値・共通テスト得点率
| 学部・学科・専攻 | 試験区分 | 偏差値 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|---|
| 医学部・医学科 | 前期 | 65.0 | 85% |
| 医学部・保健学科・看護学専攻 | 50.0 | 68% | |
| 医学部・保健学科・放射線技術科学専攻 | 55.0 | 73% | |
| 医学部・保健学科・検査技術科学専攻 | 55.0 | 73% | |
| 医学部・保健学科・理学療法学専攻 | 52.5 | 72% | |
| 医学部・保健学科・作業療法学専攻 | 52.5 | 71% |
医学部医学科の共通テスト得点率は85%で他の学科よりも高い得点が求められることが分かります。
一方保健学科では放射線技術科学専攻と検査技術科学専攻の偏差値が高く、共通テスト得点率も、保健学科の中では高いことが分かりました。
倍率
| 学部・学科・専攻 | 入試名 | 倍率 |
|---|---|---|
| 医学部・医学科 | 前期日程 | 3.5 |
| 医学部・医学科 | 共通テスト課すフロンティア入試タイプⅠ | 1.8 |
| 医学部・保健学科・看護学専攻 | 前期日程 | 2.2 |
| 医学部・保健学科・看護学専攻 | 共通テスト課すフロンティア入試タイプⅠ | 0.6 |
| 医学部・保健学科・放射線技術科学専攻 | 前期日程 | 4.3 |
| 医学部・保健学科・放射線技術科学専攻 | 共通テスト課すフロンティア入試タイプⅠ | 0.3 |
| 医学部・保健学科・検査技術科学専攻 | 前期日程 | 3.1 |
| 医学部・保健学科・検査技術科学専攻医学科 | 共通テスト課すフロンティア入試タイプⅠ | 0.5 |
| 医学部・保健学科・理学療法学専攻 | 前期日程 | 3.4 |
| 医学部・保健学科・理学療法学専攻 | 共通テスト課すフロンティア入試タイプⅠ | 1.8 |
| 医学部・保健学科・作業療法学専攻 | 前期日程 | 3.0 |
| 医学部・保健学科・作業療法学専攻 | 共通テスト課すフロンティア入試タイプⅠ | ー |
医学科の倍率は例年3.5倍前後で推移しています。志願者数は2022年度までは300名を超えていましたが、2023年・2024年度は300名を切る人数となりました。
しかし、志願者数は減ったものの倍率は3倍以上をキープしているため、競争率は変わらず高いといえるでしょう。
保健学科は専攻により差がありますが、前期日程は2.2~4.3倍と放射線技術科学専攻の倍率が最も高いことが分かりました。
東北大学医学部との比較
北海道大学と東北大学はどちらも旧帝大の一角です。
偏差値を比較して、どちらの大学の難易度が高いのか調べました。
比較するのに使用するのは、河合塾の偏差値データ、進研模試の偏差値データ、東進の偏差値データ、大学偏差値研究所の偏差値データです。
| 使用するデータ | 北海道大学 | 東北大学 |
|---|---|---|
| 河合塾 | 65.0 | 67.5 |
| 進研模試 | 70 | 71 |
| 東進 | 70 | 70 |
| 大学偏差値研究所 | 70 | 72 |
表によると、河合塾、進研模試、大学偏差値研究所は東北大学の方が少し偏差値が高いとなっています。
東進のみどちらもおなじ偏差値としています。
データによって各大学の偏差値が異なります。
平均偏差値は、北海道大学が68.8で、東北大学が70.1となっています。
その為、偏差値で比較すると東北大学の方が北海道大学よりもレベルが高いといえるでしょう。
北海道大学医学部の入試情報

2024年度の北海道大学医学部の入試情報についてまとめました。
入試日程
| 方式 | 試験日 | 合格発表 | 出願期間 |
|---|---|---|---|
| 前期 | 2025年2月25日(火)・2月26日(水) | 2025年3月6日(木) | 2025年1月27日(月)~2月5日(水) |
| フロンティア入試Ⅰ | 一次:書類選考二次:2024年11月17日(日) 共テ:2025年1月18日(土)・1月19日(日) |
一次:204年11月6日(水) 二次:2024年12月10日(火) 最終:2025年2月12日(水) |
2024年9月12日(木)~9月18日(水) |
| 帰国生徒選抜日程 | 一次:書類選考 二次:2024年11月17日(日) |
一次:204年11月6日(水) 二次:2024年12月10日(火) |
2024年9月20日(金)~10月3日(木) |
| 私費外国人留学生選抜 | 一次:書類選考 二次:2024年11月17日(日) |
一次:204年11月6日(水) 二次:2024年12月10日(火) |
2024年9月20日(金)~10月3日(木) |
試験日や、出願期間が入試方式によって異なるため、確認しておくようにしましょう。
前期日程のみ試験日が違うため注意しておきましょう。
試験科目・配点
| 試験 | 数学 | 理科 | 英語 | 国語 | 地・公 | 情報 | 面接 | 総点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共テ | 60 | 60 | 60 | 80 | 40 | 300 | ||
| 二次 | 150 | 150 | 150 | ー | 75 | 525 | ||
| フロンティア入試 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | ー | 900 |
入試によって科目も配点も違うので、自分が受験する試験方法の試験科目を確認しておきましょう。
※大学入学共通テストの情報の成績は配点しません。その成績は成績同点者がいる場合の順位決定に活用します。
北海道大学医学部の入試傾向・対策

北海道大学医学部の入試傾向・対策について科目ごとにまとめました。
国語の傾向と対策
国語の入試は、主に古文や漢文が出題され、指定された文字数内でまとめて記述するスキルが要求されます。
文章を理解し、要点をつかんで記述するためには、継続的なトレーニングが不可欠です。
また、現代文の入試問題では、論展開が明確な文章が出題され、本文の趣旨をしっかりと把握したうえで的確に説明することが期待されます。
これに対応するためには、演習問題を通して、簡潔な回答をまとめるトレーニングや、古文漢文を読み解いて内容を理解する努力が必要です。
地理歴史・公民の傾向と対策
医学部受験は科目数が多いため、社会科目にはあまり勉強時間を費やすことはできません。
対策を行うにあたり、社会科目はほぼ単純暗記となるため、分散学習が有効です。
年間を通して薄く長く勉強しておけば、70%前後の得点は確実に取れるようになります。
社会は選択科目となるため、おすすめなのは「倫理、政治・経済」です。
理由は、他の社会科目よりも暗記量が少なく、短期間で効率よく高得点を目指せるためです。
また、共通テストの社会科目は得点比率が他の科目よりも配点が低いため、対策は最小限に抑えるのが得策です。
そのため、マスターするのにかかる時間が少なく暗記量も少ない「倫理、政治・経済」は対策しやすく、得点が安定しやすいでしょう。
数学の傾向と対策
出題範囲は「数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A(図形の性質、場合の数と確率)・B(数列)・C(ベクトル)」です。
数学Ⅰは 2次関数からの出題が多く、 数学Ⅱは 図形と方程式、三角関数、指数・対数関数が解法のベースとなり、相加平均と相乗平均の関係にも注意が必要です。
数学Ⅲは 複素数平面、数列の極限、関数の極限、微・積分法が重要となり、積分法では計算力が要求されています。
数学Aは確率からの出題が多く、数列との融合問題も頻繁にあります。
数学Bのベクトルは内積を含む問題が多く、数列では漸化式と数学的帰納法に注意しましょう。
問題は2、3の小問に分かれており、解答の過程が重視され、明確で整理された答案が求められます。
全体的には標準問題が多く、学習成果が反映されるものの、近年はやや難解な問題も増えていましたが、2024年度は従来のレベルに戻りました。
基本事項を教科書や傍用問題集で確認し、代表的な活用例もしっかりとマスターしておきましょう。
入試問題ではいくつかの基本事項が融合されているため、スムーズな基本事項の活用が重要です。
基本事項を習得したら、標準問題が中心の入試問題集で基本事項を自在に扱う練習を行いましょう。
標準問題の解答が合格の鍵となります。
さらに、論理的でポイントを押さえた答案作成力を養い、正確な図の描画も習慣づけてください。
最後に、過去問や北海道大学の入試に対応した模試などで出題傾向に慣れるために取り組みましょう。
問題演習では、頻出の分野に焦点を当てて学習し、証明問題は全分野にわたって出題される可能性があるため、十分な練習が必要です。
理科の傾向と対策
物理基礎・物理の出題範囲では力学と電磁気が中心で、力学では振り子や円運動、衝突、慣性力が頻出です。
運動保存則や力学的エネルギー保存則も毎年のように出題されます。
電磁気ではコンデンサーと電磁誘導がよく取り上げられ、熱力学も気体の分子運動などが出題されます。
波動では弦の振動や回折格子に関する問題があります。
問題は後半に思考や計算を要するものが配置され、誘導的な設問が多いです。
全体としては標準的な難易度であり、物理的思考力と正確な計算力が要求されます。
教科書を中心に基本事項を理解し、公式や法則を整理し、問題練習を通じて確実に理解を深めることが重要です。
難問にこだわらず、市販の問題集を通して物理の原則をしっかりと身につけることが勧められます。
描図問題に対する対策として、代表的なグラフや模式図を見なくても描けるようにし、実践的な練習を積み重ねることが必要です。
論述問題においては結果を当たり前とせず、20〜30字で説明できるよう心がけ、計算過程も明確に記述することが重要です。
化学分野では、化学基礎・化学に関する記述・計算・選択問題が出題されます。
理論、無機、有機の分野から幅広い内容で、理論と関連する総合問題もあります。
問題文の読解が求められ、全分野にわたる理論問題や計算問題があります。
2021年度では生成速度や溶解度積を用いたpHの計算がありました。
無機分野では気体、金属、金属イオンの反応が重要で、単体・化合物の性質は周期表とも関連して出題されています。
有機分野ではさまざまな有機化合物の反応や性質、構造推定があり、思考力が必要です。
問題の難易度は標準からやや難のレベルで、正確な計算力や幅広い知識が必要です。
特に理論分野では用語や法則の理解が重要で、計算問題のウエートも大きいため基礎から幅広く練習が必要です。
無機分野では単体・化合物の性質と反応を把握し、有機分野では構造・性質・反応に焦点を当てた練習が必要です。
実験やグラフを扱う問題もあるため、教科書の内容に注意を払い、実践的な準備をお勧めします。
生物分野の出題形式は主に記述・選択・論述問題で、計算問題も含まれます。
論述問題には字数制限があり、描図問題も2019・2022年度に出題されました。
生物基礎・生物の出題範囲では、2024年度は遺伝情報、細胞、代謝、生殖・発生、進化・系統、生態などから問題が出され、大問が複数の分野をカバーすることが一般的です。
難易度は標準〜やや難で、実験からの考察問題や論述問題が結果に影響する可能性があります。
記述問題では難しい内容はほとんどなく、まずは教科書に基づいて学習を進めていくとよいでしょう。
生物用語の記述問題が多いため、定義を含めて正確に覚え、論述問題でも適切に使用できるようにすることが重要です。
実験結果から意味を考察し、分析力を養うためには問題集や他大学の過去問を多く解くと効果的です。
数年間の過去問を解くと、同じテーマが形式を変えて出題されたり、他の分野との関連が見受けられます。
早い時期から過去問に取り組み、出題形式や苦手分野を把握し、時間配分の感覚を身につけることが大切です。
英語の傾向と対策
出題形式は、読解が2題、読解・英作文が1題、会話文が1題で構成されており、解答形式は記述式と選択式があります。
記述式では、英文和訳と内容説明、意見論述などの高度な記述力が求められますが、単語や語句で答えることもあります。
読解問題では、内容説明に字数制限があり、英作文では語数制限付きの意見論述が通例です。
選択式では同意表現や、内容説明、内容真偽、読解英文や会話文の要約分の空所補充などが出題されます。
読解問題では幅広い分野の英文が取り上げられ、文脈を考慮した内容理解が問われます。
読解英文の分量は例年1題700語前後のことが多いですが、2023年度が2題合わせて1600語を超え、2024年度は2題とも約680語でした。
読解・英作文問題では英文を読んで内容説明や段落の要約、意見論述を行います。
内容説明は空所補充形式で行われます。
会話文問題では、会話文の要約の空所を選択肢から補充し、意味だけでなく、文法・語彙の知識を文脈に結びつける能力が求められます。
出題の難易度は、試験時間に対して、読解英文の量が多く、意見論述に手間取りやすいことから時間配分には特に気を付ける必要があります。
読解問題に対する対策として、まずは語彙力の向上に注力しましょう。
読解や英作文の基本は語彙力です。
読解練習で出てくる単語や熟語をノートにまとめ、文脈の中で理解することで実戦的な語彙力が身につきます。
解答は適切な日本語でまとめる練習も必要です。
記述式の問題集を利用して、自分で解答を書く練習を行いましょう。
会話文問題に対する対策として、長文で時事的なテーマが出題されることがあり、議論に近いものもあります。
読解問題の対策を基に、長い会話文の読解に挑戦し、会話や議論の展開、各人物の主張やその変化について正確に把握できるように練習しましょう。
まとめ
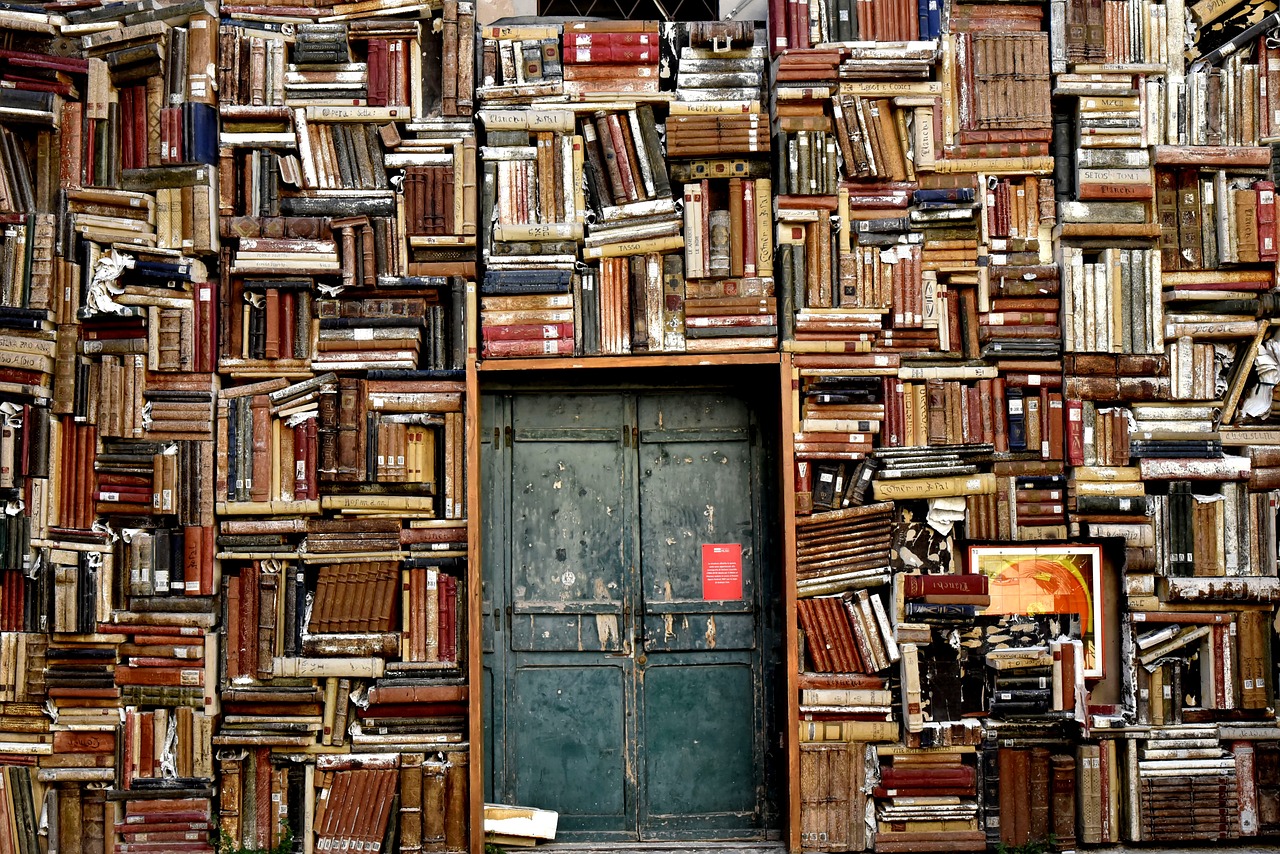
今回は、北海道大学医学部について解説いたしましたがいかがでしたでしょうか。
北海道大学は、幅広い領域にわたる総合的な教育を提供しています。
基礎医学から、臨床医学まで包括的な知識と、スキルの習得をすることが出来ます。
北海道大学医学部が気になられた方は、是非受験を検討してみてください。
早い段階から受験対策をし、合格をつかみましょう。
公式サイト:北海道大学
この記事の執筆者:医進の会代表 谷本秀樹

大学入試は四谷学院などの大手予備校や多くの医学部受験予備校で、主に生物の集団授業と個別授業で300人以上の受験生を担当。
自身の予備校『医進の会』発足後は、これまで500人以上の生徒の受験と進路指導に携わってきた。
『個別の会』の代表でもあり、圧倒的な医学部入試情報量と経験値、最適なアドバイスで数多くの受験生を医学部合格に導いてきた、医学部予備校界屈指のカリスマ塾長。

