勉強中におすすめの飲み物12選!やる気や集中力が高まる飲み物の選び方や注意点も解説
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:基礎知識

「勉強のときの飲み物はなにがおすすめ?」「勉強中に飲み物を摂る効果は?」「勉強中に飲み物を飲むときの注意点が知りたい!」
上記のように、勉強中の飲み物について疑問点などはないでしょうか。
勉強中に摂る飲み物は、種類や飲み方によって、学習効率などを低下させます。
そのため、勉強中の飲み物について正しい知識を身につける必要があります。
本記事では、勉強中におすすめの飲み物をご紹介します。
また、飲み物の選び方や注意点なども解説します。
勉強中の飲み物について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
勉強中に飲み物を飲む目的
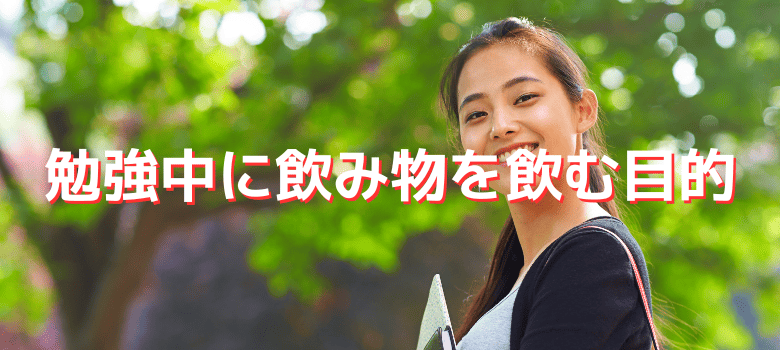
勉強中に飲み物を飲む目的として、3つの内容を解説します。
単にのどが渇いたから飲むだけではなく、さまざまな目的を理解して置くことで重要性を理解できます。
水分の補給
勉強中に水分の補給をすることは、脳や身体の機能を維持するために重要です。
人間の体は約60%が水分で構成されており、脳は約80%が水分です。
水分が不足すると、血液の循環や代謝が低下し、脳への酸素や栄養素の供給が減少します。
これにより、集中力や記憶力、判断力などの認知能力が低下する可能性があります。
また、水分不足は頭痛や倦怠感、イライラなどの不快な症状を引き起こすこともあります。
これらの症状は勉強の効率や質を低下させる要因となります。
水分の補給は、一定の間隔で少量ずつ行うことが望ましいです。
一気に大量に飲むと、体内の水分バランスが崩れたり、頻尿になったりすることがあります。
エネルギーの補給
勉強中にエネルギーの補給をすることは、脳や身体の疲労を回復させるために有効です。
脳はエネルギー消費量が高く、体重の数%しかないにもかかわらず、全身のエネルギー消費量の20~25%を占めています。
勉強は脳に負担をかける活動であり、長時間行うとエネルギー源であるブドウ糖が不足することがあります。
ブドウ糖が不足すると、認知能力や学習能力が低下する可能性があります。
エネルギーの補給は、飲み物だけでなく食べ物も含めて考える必要があります。
飲み物だけでエネルギーを摂取する場合は、砂糖やカフェインなどの刺激物を含むものは避けましょう。
これらの成分は一時的にエネルギーを上げる効果がありますが、その後にエネルギー低下や依存性などの副作用を引き起こす可能性があります。
代わりに、水やお茶などの無糖の飲み物に、果物やナッツなどの健康的な食べ物を組み合わせることがおすすめです。
これらの食べ物は、ブドウ糖やビタミン、ミネラルなどの脳に必要な栄養素をバランスよく提供し、持続的なエネルギーを生み出します。
集中力やモチベーションの向上
勉強中に飲み物を飲むことは、集中力やモチベーションを向上させるためにも役立ちます。
飲み物を飲むことで、口の中や喉の温度や湿度が変化し、脳に刺激を与えることが可能です。
これにより、脳の覚醒度が高まり、集中力が増す効果が期待できます。
また、飲み物を飲むことで、自分へのご褒美や気分転換にもなります。
結果として勉強に対するモチベーションが高まり、学習効果が向上するでしょう。
飲み物の種類や味も重要であり、これが集中力やモチベーションに影響を与えます。
飲み物の種類に関しては後のテーマで詳しく解説します。
勉強中の飲み物の選び方

ここからは、勉強中の飲み物の選び方を解説します。
勉強中の飲み物を選ぶときは、これから解説する3点に着目しましょう。
コスパを重視する
勉強中に飲み物を選ぶ際に、コスパ(コストパフォーマンス)を重視することは、経済的にも効率的にもメリットがあります。
コスパの高い飲み物とは、価格が安くて量が多く、栄養価や味も優れているものです。
コスパの高い飲み物を選ぶことで、お金を節約できるだけでなく、水分やエネルギーの補給も十分にできます。
また、コスパの高い飲み物は、粉末状など自宅で作ることができる場合が多いです。
自宅で作ることで、好きな味や温度に調整できるだけでなく、衛生面や保存性も安心できます。
コスパの高い飲み物の例としては、水やお茶、牛乳、豆乳、果汁100%のジュースなどが挙げられます。
これらの飲み物は、スーパーやコンビニなどで安く購入できる場合が多く、1本や1リットルあたりの単価も低いです。
容器の種類で選ぶ
勉強中に飲み物を選ぶ際に、容器の種類にも注意することが大切です。
容器の種類によっては、飲みやすさや持ち運びやすさ、保温性や保冷性などが異なります。
容器の種類には大きく分けて、ペットボトルや缶、紙パックやカップなどがあります。
容器の種類を選ぶ際には、自分の勉強スタイルに合わせて選ぶことがおすすめです。
例えば、外出先で勉強する場合は、ペットボトルや缶が便利ですが、自宅で勉強する場合は、紙パックやカップが良いでしょう。
人気商品を比較する
勉強中に飲み物を選ぶ際に、人気商品を比較することも参考になります。
人気商品とは、売上や口コミなどで高い評価を得ている商品のことです。
人気商品を比較することで、自分の好みや目的に合った商品を見つけることができます。
人気商品を比較する際には、インターネットや雑誌などのメディアを活用することが便利です。
これらの情報を参考にすることで、飲み物の特徴やメリット・デメリットなどを知ることができます。
また、季節やイベントなどに合わせた飲み物の特集やキャンペーンなども行われており、飲み物のバリエーションや楽しみ方を知ることも可能です。
人気商品は多くの人に支持されているからといって、必ずしも自分に合っているとは限りません。
自分の判断力や好奇心を持って、自分に合った飲み物を選ぶことが大切です。
勉強中におすすめの飲み物12選
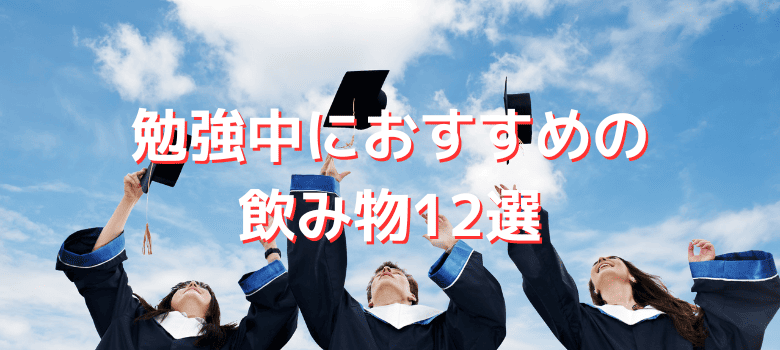
勉強中におすすめの飲み物として、12種類の飲み物をご紹介します。
疲労回復や集中力向上など、カテゴリー別にまとめました。
目的に応じて選んでみてください。
疲労回復に効果的な飲み物
疲労回復に効果が期待できる飲み物は豆乳、野菜ジュース、柑橘系の果汁100%ジュースです。
それぞれの特徴や効果をみていきましょう。
豆乳
豆乳は、大豆から作られた植物性の飲み物です。
豆乳には、タンパク質やカルシウム、ビタミンB群などの栄養素が豊富に含まれています。
これらの栄養素は、疲労回復に欠かせないものです。
タンパク質は、筋肉や血液などの体組織の構成要素であり、エネルギー源にもなります。
カルシウムは、骨や歯の健康を保つだけでなく、神経や筋肉の働きを正常にするためにも必要です。
野菜ジュース
野菜ジュースは、野菜から絞ったり加工したりした飲み物です。
野菜ジュースには、ビタミンCやカロテン、鉄分などの栄養素が多く含まれています。
カロテンは抗酸化作用があり、細胞の老化を防ぐ効果があります。
自宅で作る場合は、添加物を避けることができる点がメリットです。
柑橘系の果汁100%ジュース
柑橘系の果汁100%ジュースとは、オレンジやグレープフルーツなどの柑橘類の果汁だけで作られた飲み物です。
柑橘系の果汁100%ジュースには、ビタミンCやクエン酸などの栄養素が豊富に含まれています。
冷やすことでさらに爽やかな味わいになります。
集中力の向上に効果的な飲み物
集中力の向上に効果が期待できる飲み物は牛乳、コーヒー、ココアです。
それぞれの特徴や効果をみていきましょう。
牛乳
牛乳は、勉強中に飲むと集中力を高めることができる飲み物です。
牛乳には、カルシウムやビタミンB群が豊富に含まれています。
これらの栄養素は、脳や神経の働きをサポートする効果があります。
コーヒーやお茶
コーヒーやお茶は、カフェインを含む飲み物です。
カフェインには、集中力や記憶力を向上させる効果があります。
砂糖やハチミツなどを加えることで、ブドウ糖を補給することも可能です。
ココア
ココアは、チョコレートの原料であるカカオ豆から作られた飲み物です。
ココアには、カフェインやフラバノールが含まれています。
これらの成分は、眠気を払い、集中力や記憶力を高める効果があります。
眠気を覚ましやすい飲み物
眠気を覚ましやすい飲み物はドリップコーヒー、緑茶、ミントティーです。
それぞれの特徴や効果をみていきましょう。
ドリップコーヒー
ドリップコーヒーは、コーヒー豆を挽いてお湯で抽出した飲み物です。
カフェインを多く含み、覚醒作用が強い点が特徴です。
緑茶
緑茶は、茶葉を発酵させずに加工した飲み物です。
緑茶には、カフェインとテアニンが含まれており、リラックス効果と集中力向上効果があります。
ミントティー
ミントティーは、ミントの葉や茎から抽出した飲み物です。
メントールは冷涼感を与え、嗅覚や味覚に刺激を与えて眠気を覚ます効果があります。
勉強中の生理痛を和らげる飲み物
女性にとっては勉強中の生理痛によって集中力が低下したり、勉強そのものができなくなったりします。
生理痛を和らげる飲み物として、ホット豆乳、ヨモギ茶、しょうが湯をご紹介します。
ホット豆乳
ホット豆乳は、大豆から作られた植物性の飲み物です。
ホット豆乳には、大豆イソフラボンという女性ホルモンに似た作用を持つ成分が含まれています。
温かい飲み物は血行を良くし、生理痛を和らげます。
ヨモギ茶
ヨモギ茶は、日本では春先によく見かける薬草であるヨモギから作られた飲み物です。
ヨモギ茶には、ビタミンAやビタミンCが含まれており、免疫力を高めたり血液をサラサラにする効果があります。
しょうが湯
しょうが湯は、生姜をすりおろしてお湯で割った飲み物です。
しょうが湯には、ジンゲロールやショウガオールが含まれ、体を内側から温める効果があります。
勉強中に飲み物を飲むときの注意点
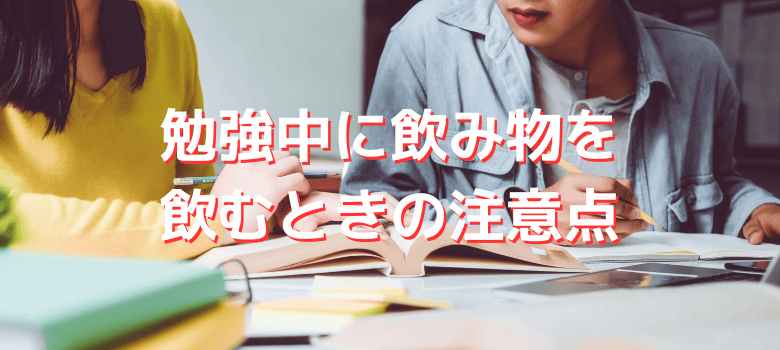
勉強中に飲み物を飲むときの注意点を押さえておきましょう。
注意点として4点を解説します。
それぞれの内容を確認して、勉強中の飲み物を飲むときに注意してください。
カフェインを摂り過ぎない
カフェインは、コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれる成分で、覚醒作用や集中力向上作用があります。
勉強中に眠気を覚ますためにカフェインを摂取するのは悪くありませんが、摂り過ぎると逆効果です。
カフェインの過剰摂取による症状には、頭痛や不安、動悸や不眠などがあります。
これらの症状は勉強の効率を下げるだけでなく、健康にも悪影響を及ぼします。
なお、カフェインの摂取量の目安は、ドリップコーヒーならば1日2杯程度です。
飲むタイミングも気を付ける
勉強中に飲み物を飲むタイミングも重要です。
飲み物を飲むことで水分補給やエネルギー補給ができますが、飲むタイミングによっては逆効果になることもあります。
例えば、甘い飲み物を一度に大量に飲むと血糖値が急上昇し、その後急降下することで眠気や集中力低下の原因となります。
甘い飲み物は少しずつ飲み、血糖値の上昇を緩やかにする工夫をしましょう。
スポーツドリンクを避ける
スポーツドリンクは、運動中に失われる水分や電解質を補給するために作られた飲み物です。
しかし、勉強中にスポーツドリンクを飲むのはおすすめできません。
運動しない状態で飲むとカロリーオーバーになる可能性があるからです。
また、甘味料や香料などの添加物が健康に悪影響を及ぼすこともあります。
水やお茶などの無糖の飲み物を選ぶのが良いでしょう。
一度に大量の飲み物を飲まない
勉強中に水分補給することは大切ですが、一度に大量の飲み物を飲むことは避けましょう。
一度に大量の飲み物を飲むと、胃が膨らんで眠気やだるさを感じるなどのデメリットがあります。
さらに、頻尿や血圧の低下によるめまいなども起こり得ます。
水分補給は、少しずつ口に含む形で行うのがおすすめです。
まとめ

勉強中に飲み物を飲むことにはさまざまな目的があります。
水分や栄養分を補給して勉強の効率化やモチベーションを向上させるメリットも考えられます。
とはいえ、飲み物は多種多様にあるため、目的に応じて飲みましょう。
今回は目的別におすすめの飲み物をご紹介しました。
飲むときの注意点を踏まえて、効果的に飲んで、学習効果を高めましょう。
この記事の執筆者:医進の会代表 谷本秀樹

大学入試は四谷学院などの大手予備校や多くの医学部受験予備校で、主に生物の集団授業と個別授業で300人以上の受験生を担当。
自身の予備校『医進の会』発足後は、これまで500人以上の生徒の受験と進路指導に携わってきた。
『個別の会』の代表でもあり、圧倒的な医学部入試情報量と経験値、最適なアドバイスで数多くの受験生を医学部合格に導いてきた、医学部予備校界屈指のカリスマ塾長。

