勉強すると眠くなるのはなぜ?原因と対策・対処方法を解説
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:基礎知識
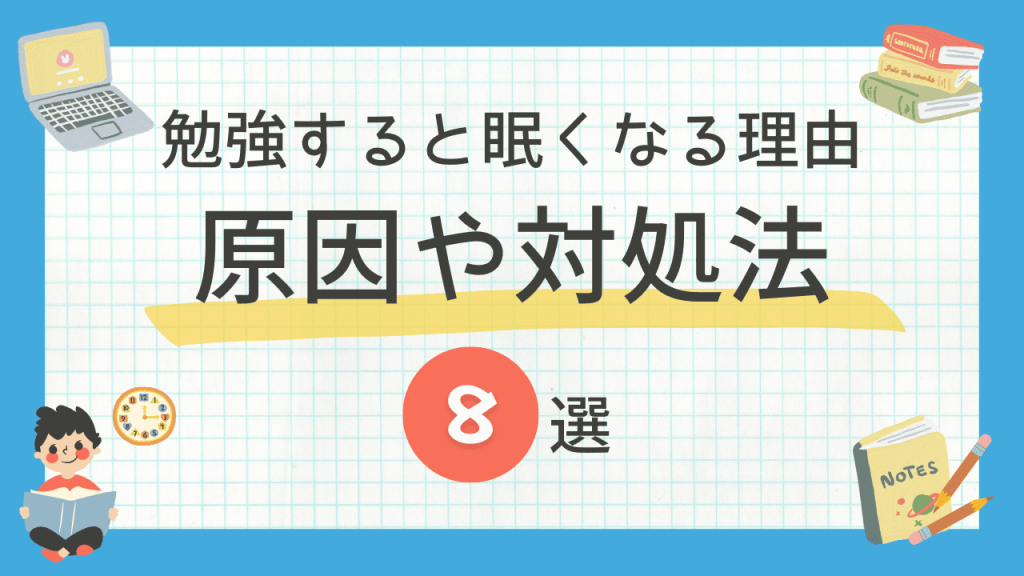
勉強をしている最中に眠くなった経験をお持ちでしょうか。
眠くなるタイミングは人それぞれですが、夜中ならともかく、昼間であっても眠くなるのは不思議なものです。
実は、勉強中に眠くなるのにはきちんとした理由があります。
そこで、今回は勉強すると眠くなる原因について詳しく紹介します。
また、勉強中に眠くならないための対策方法や眠くなってしまったときの対処方法についても、一緒に取り上げるため、ぜひ最後までご覧ください。
勉強すると眠くなる原因
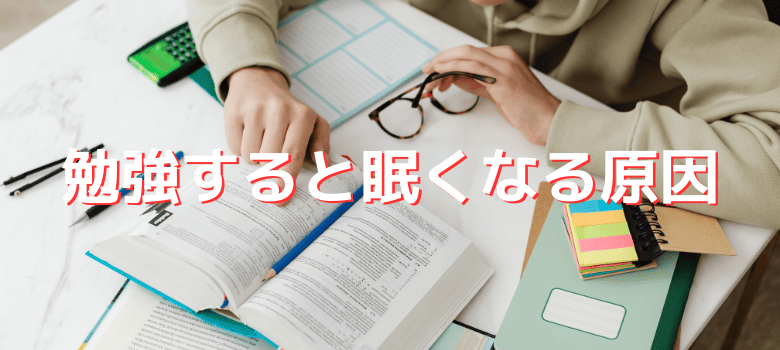
それでは、勉強中の眠気の原因について解説します。
勉強中にどうしても眠くなってしまう原因は、主に以下の6つであることが多いです。
順番に解説します。
睡眠時間が不足している
眠気に悩まされている場合は、まずは自身の睡眠から見直すようにしましょう。
勉強中に眠くなってしまう原因のなかで、最もありがちなのが睡眠時間の不足です。
理想の睡眠時間については諸説ありますが、中高生の場合8時間以上が望ましいとされています。
しかし、普段の勉強時間などを考慮すると、現実的なのは7時間以上でしょう。
学生の多くは、テストや試験の直前にいつもより長く勉強時間を確保して、追い込みをかけています。
時間を捻出する際、削られやすいのが睡眠時間です。
睡眠時間をきちんと確保できないと、勉強で疲れている頭や体が休まることはありません。
結果、日中に強烈な眠気に襲われてしまいます。
また、眠る直前までスマートフォンやパソコンを触っている人も、睡眠に問題がある可能性が高いです。
液晶画面からのブルーライトが、睡眠を促進する脳内物質のメラトニンの生成を妨げ、睡眠の質に悪影響を与えます。
血糖値が低くなっている
食後に眠気を感じた経験をお持ちではないでしょうか。
実は、食後の眠気には、血糖値が関係しています。
血糖値とは、血液中に含まれているブドウ糖、グルコースの濃度のことです。
食事の前後で血糖値は大きく変動しますが、血糖値が下がると人は眠気やだるさを感じます。
これは、食事を沢山摂取することで、急激に血糖値が上昇し、過剰にインスリンが分泌されるためです。
インスリンには血糖値を下げる効果があり、血糖値が下がると、脳に供給されるブドウ糖が不足し、結果人は強い眠気に襲われます。
低血糖は眠気だけでなく、集中力の低下や脱力感、疲労感など、さまざまな症状を引き起こすため、眠気以外の自覚症状がある場合は注意しましょう。
ちなみに、低血糖が原因で眠くなる場合は、ブドウ糖を摂取することで眠気を解消できます。
脳の血流が低下している
夜だけでなく、日中でも眠くなる人は、脳の血流が低下している可能性が考えられます.
血流とは、心臓から出た血液が全身の血管を巡り、再び心臓に戻る流れのことです.
血液は栄養素や酸素、体内で生み出された熱などを全身に運ぶという重要な役割を担っています.
脳の血流は疲労の程度を測るひとつの指標です.
血流が顕著に低下すると、脳が休むための命令を出し、 人は眠気を感じます.
血流の低下は、眠気を含め疲労感やむくみ、冷え性など、さまざまな症状を引き起こす原因です.
血流はストレスや食生活の乱れ、運動不足などによって低下しますが、どの理由も勉強に注力しているときと密接に関係しています.
また、血流の低下が続く場合は、自律神経失調症も疑いましょう.
自律神経失調症は放っておくと、うつ病やパニック障害などの精神疾患、そして不整脈や糖尿病などの心身症を招く原因となるため、注意が必要です.
脳の温度が上がりすぎている
脳の温度を意味する「脳温」という言葉をご存知でしょうか。
実は、この脳温も眠気と密接な関係があります。
一般的に、脳温が上昇するのは頭が興奮状態にあるときです。
不安や悩みによるストレスや疲労、肉体労働による身体的ストレスが増えると、脳は発熱します。
勉強をしているときも、プレッシャーや疲労を感じて脳温が上がりやすいです。
脳温が上がると、脳はオーバーヒート状態となります。
脳がオーバーヒートを起こして働きが鈍くなると、体内のコントロールが乱れ上手く機能しません。
すると、発熱やだるさ、集中力の低下などの症状が現れ、パフォーマンスが大きく低下してしまいます。
そのため、脳が身体の正常な状態を取り戻そうとして、強制的に休ませるために眠気を感じさせているのです.
ストレスで拒否反応を示している
人は、ゲームやスポーツに代表される魅力的な刺激に接しているとき、脳が活性化するドーパミンと呼ばれる物質が分泌され、覚醒状態となります。
遊んでいるときに眠くならず、元気になるのはこのドーパミンが原因です。
一方で、刺激が少なかったり、強いストレスを感じたりすると眠気を感じやすくなります。
とくに勉強をしているときは、結果を残したいという気持ちがストレス、プレッシャーとなり、
自身の心身を守る回避行動として、脳が眠気を引き起こすケースが多いです。
しかし、多くの学生は眠気の原因に気がつきません。
また、周囲の人からは「やる気がない」「勉強をサボっている」と指摘され、余計にストレスが溜まり、
眠くなるという負のループに嵌ってしまう場合もあります.
自己防衛本能が働いている
人は過度なストレスを感じると、防衛本能が働き、その場から逃げ出したいと感じます。
防衛本能とは、その名のとおり人が危機に直面した際に受ける苦痛を軽減させるために、無意識下で作用する心理的なメカニズムです。
自己防衛反応には、逃避行動や理由の合理化など、さまざまな種類があり、眠気も防衛反応のひとつといわれています。
たとえば、勉強会などで話を聞いているとき、特定の話題で強烈な眠気に襲われている場合、
防衛本能が働いている可能性が高いです。
そもそも人は大きな変化を好まず、自身がすでに持っている情報で物事を対処しようとする生き物のため、
勉強や変化の過程において防衛本能が働くことは多々あります。
その勉強や変化が、自身にとって不都合な内容であれば、なおさらです。
勉強中に眠くならないための対策方法
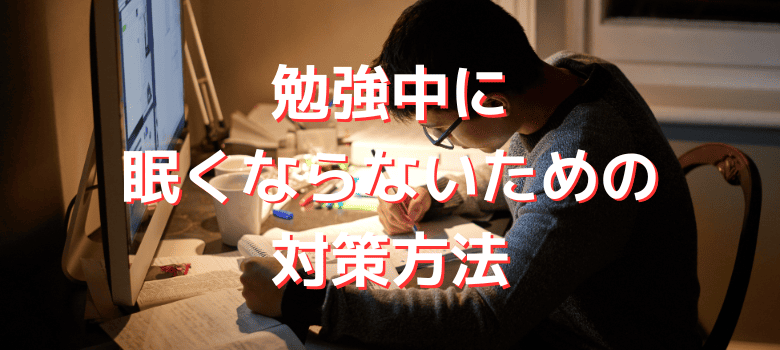
根本的な原因を取り除けば、勉強中の眠気をある程度予防できるでしょう。
続いては、勉強中に眠くならないための方法について紹介します。
睡眠の質を高める
眠気の原因となりやすい睡眠不足については、睡眠の質を高めることで対処できます。
良質な睡眠とは、寝つきが良く、ぐっすり眠り、そして寝起きがスッキリしていることが条件です。
睡眠の質の向上に成功すれば、勉強中の眠気の予防だけでなく、勉強自体のパフォーマンスもアップするでしょう。
睡眠の質を高めるためには、体温を上手くコントロールすることが重要です。
睡眠と体温には深い関係があり、身体の内側の体温である深部体温が下がると、脳と身体は休憩モードに入ります。
そして、深部体温が急速に下がると、深い眠りに落ちやすいです。
そのため、寝る前に深部体温を上げる工夫をすると、寝付きに良い影響を与えるでしょう。
たとえば、寝る前にぬるめのお湯に浸かると、深部体温を上げるだけでなく、リラックス効果も期待できます。
ただし、熱すぎるお湯に浸かると体の覚醒を誘ってしまうため、
38度のお湯に、5分から30分浸かる程度にとどめておきましょう.
規則正しい食生活を心がける
規則正しい食生活も、良質な睡眠には欠かせません。
就寝に近い時間の食事は、身体が消化活動を優先してしまい、内臓が休まらず、睡眠を妨げてしまうため避けてください。
良質な睡眠のためにも、就寝時点で内臓の消化活動がすべて終わっているのが理想です。
そのため、就寝の3時間前には夕食を済ませるようにしましょう。
また、食事の内容にも注意が必要です。
たとえば、揚げ物やラーメン、焼肉などの脂っこい食事は消化に時間がかかるため、
食事の時間が遅くなる場合は、避けることをおすすめします.
飲み物については、自然な眠気を誘発できる温かい飲み物を就寝前に飲むようにしましょう.
白湯や生姜湯などの暖かい飲み物、そしてリラックス効果の期待ができるハーブティーなどがおすすめです.
一方で、緑茶やコーヒーなどは、カフェインが含まれているため覚醒作用があります.
敏感な人は、就寝の5時間から6時間前の時間帯には摂取しないようにしましょう.
塾や図書館で勉強する
集中力が低下します。
結果、眠気に襲われやすくなりがちです。
その場合、勉強する環境を変えるとよいでしょう。
自室以外の場所、たとえばリビングやダイニングなどは家族の目もあるため、集中して勉強に取り組みやすいです。
図書室や塾の学習塾もおすすめです。
自身と同じように勉強をしている人が周囲にいる環境は刺激となり、勉強の効率の向上効果も期待できます。
また、最近は有料自習室の存在も一般的になりました。
多くの場合は月額料金をあらかじめ支払いますが、
1日単位で利用できる有料自習室もあります。
平日はもちろん、土日や祝日でも利用でき、かつインターネット利用ができる有料自習室も珍しくないため、
近くにある場合は積極的に利用してみましょう.
運動習慣を身につける
運動習慣がある人は、運動習慣がない人と比べて不眠が少ないことがわかっています。
そのため、勉強の合間に運動をするようにしましょう。
良質な睡眠のためには、行う運動の内容や強度も重要です。
不定期に行う運動よりも、習慣的に続ける運動の方が睡眠によい影響を与えます。
たとえば、ジョギングなどは運動になるだけでなく、勉強の気分転換にも効果的です。
運動のタイミングは勉強に疲れたときでも問題ありませんが、
より高い効果を期待している場合は、夕方から夜の就寝の3時間前に運動をするようにしましょう。
就寝の数時間前に、一時的に体温を上げているのがポイントです。
ただし、激しすぎる運動は逆に睡眠を妨げてしまいます。
負担が少なく、長続きする運動習慣を身につけましょう.
勉強中に眠くなった場合の対処方法
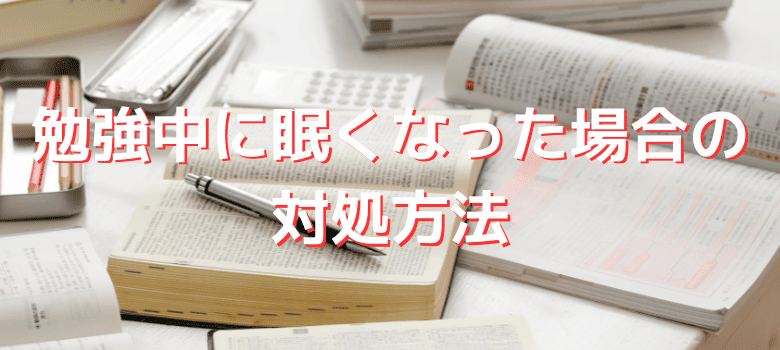
睡眠や食事など、生活習慣を見直せば、ある程度勉強中の眠気を防げますが、完全に眠気から解放されるわけではありません。
もし勉強中に眠くなったら、以下の対処方法を試してみましょう.
ストレッチで身体を動かす
ストレッチは血行をよくして、眠気を覚ます効果があります.
そのため、勉強の最中に眠気を感じたらストレッチを行ってみましょう.
背伸びをする、肩を回す、太ももの裏を伸ばすなど、椅子に座ったままでも行えるストレッチは多数あります.
眠気を感じたときに重点的に行いたいのが、肩や足首、ふくらはぎのストレッチです.
とくに、足元が温まっていると余計に眠気を感じやすくなるため、素足の状態でストレッチを行うことをおすすめします.
また、部屋以外の場所でストレッチをする際は、周囲の人の邪魔にならないようにしましょう.
短時間の仮眠を取る
どうしても眠気が取れない場合は、思い切って仮眠を取ってしまいましょう.
仮眠を取る際は、長くても20分程度にとどめてください.
20分以上の仮眠は、身体が熟睡モードに入ってしまい、パフォーマンスが顕著に落ちてしまいます.
また、仮眠を取る前にコーヒーや緑茶など、カフェインを含む飲み物をあらかじめ飲んでおきましょう.
疲労が溜まっている状態で仮眠を取ると、深く眠りすぎて目覚めにくい場合があります.
カフェインは摂取してから30分後に効果を発揮するため、仮眠後の目覚めをサポートしてくれるでしょう.
勉強する環境を変える
勉強する環境を変えてみるのもおすすめの方法です.
自宅であればリビングやダイニング、学校であれば図書室などで勉強をしてみましょう.
場所を移動するだけでも、勉強の効率は大幅に変化します.
もし時間に余裕があれば、部屋の模様替えを行うのもよいでしょう.
ポイントとしては、勉強する机の周辺には、必要最低限のものだけ置くようにしてください.
とくにスマートフォンや携帯ゲーム機、漫画などを置くのは厳禁です.
また、圧迫感を感じて勉強に集中できない人も多いため、机の配置は壁に寄せすぎないようにしましょう.
空いたスペースに収納ボックスを配置すれば、作業効率を上げることもできます.
勉強の内容や教科を変える
眠気を感じているときは、勉強に飽きてしまっている可能性が高いです.
その場合、勉強している教科を変更するとよいでしょう.
複数の教科を切り替えながら行うことで、刺激を受ける脳の部分が変化し、眠くなるのを防ぐ効果が期待できます.
また、同じ教科でも、英単語の暗記から文法問題に変える、現代文から古典に変えるなど、勉強の内容を変えるのも効果的です.
洗顔や入浴などでリフレッシュする
強い眠気を解消するためには、洗顔や入浴でリフレッシュするのもおすすめです.
顔や手には、多くの知覚神経が集まっています.
そのため、顔や手をなるべく冷たい水で洗うと、脳に刺激がいき、眠気を解消することが出来ます.
また、歯磨きも手を動かす行為によって頭が覚醒するため、眠気覚ましに効果があります.
その際、口の中がスッキリするミント系の歯磨き粉を使用するのがおすすめです.
声に出して勉強する
眠気に打ち勝つためには、声を出して勉強するのもよいでしょう.
テキストや単語を声に出すと、視覚と聴覚が刺激され脳を覚醒させることが可能です.
声を出す勉強方法は、眠気覚ましだけではなく、記憶が定着しやすいという特徴があります.
このとき、耳を塞ぎながら声を出すと、骨伝導効果により脳全体をより活性化させることが可能です.
また、英語の勉強の場合は正しい発音を自分で繰り返すことで、リスニングの強化にも効果があります.
英語の聞き取りに自信がない人は、積極的に声を出して勉強してみましょう.
耳を引っ張る
人の身体には多数のツボが存在しており、ツボを刺激することで、さまざまな効果が期待されます.
耳たぶもツボは存在しており、このツボを刺激すると眠気が覚めやすくなるため、勉強の合間に触るとよいでしょう.
やり方は両手で左右の耳たぶを持ち、下にゆっくり3秒引っ張ったあとに離すだけです.
これを5回ほど繰り返してください.
また、耳たぶにあるツボは眠気を覚ますだけでなく、脳の疲れを解消する効果もあります.
首や脇の下を冷やす
体温が上がりすぎると、強い眠気に襲われやすくなります.
そのため、首や脇の下など、太い血管が通っている場所を冷やして、体温を下げるようにしましょう.
夏場は熱中症対策にもなるため、おすすめです.
冷やす際は凍ったペットボトルや缶、冷たい水で冷やしたタオルなどを使用しましょう.
また、最近は薬局などで冷却シートや冷却スプレーなども購入できるようになっているため、必要に応じて活用してください.
ただし、使用する際は説明書に記載されている注意点を守りながら使いましょう.
眠気がなくても勉強が手につかず、困っている人もいるのではないでしょうか.
勉強ができない人の特徴やできるようになる方法について、こちらで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください.
まとめ
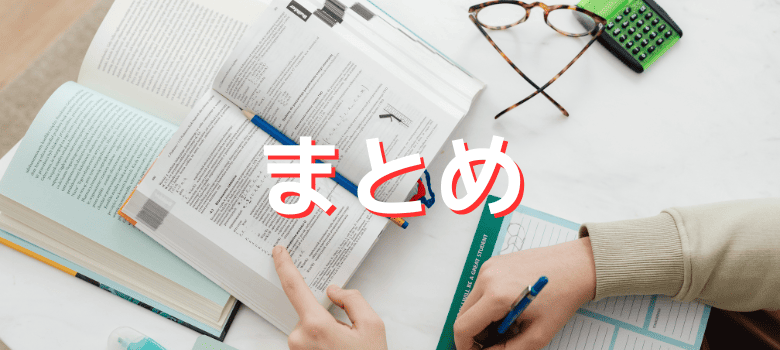
以上、勉強すると眠くなる原因、そして眠気に対する対策と対処方法について解説しました。
眠気の根本的な原因の多くは、長時間の勉強による生活リズムや食習慣の乱れによるものです。
勉強をするにあたって、勉強のせいで学習効率が落ちてしまっては意味がありません。
そのため、眠気に悩まされている場合は生活習慣をしっかり見直すことをおすすめします。
勉強の環境を整えたい場合は、予備校へ通うのもひとつの手です。
自習室など勉強に集中しやすい設備が用意されているだけでなく、受験対策に特化したカリキュラムによって効率的な勉強ができるため、興味を持った人は、ぜひ一度医進の会へご連絡ください.
この記事の執筆者:医進の会代表 谷本秀樹

大学入試は四谷学院などの大手予備校や多くの医学部受験予備校で、主に生物の集団授業と個別授業で300人以上の受験生を担当。
自身の予備校『医進の会』発足後は、これまで500人以上の生徒の受験と進路指導に携わってきた。
『個別の会』の代表でもあり、圧倒的な医学部入試情報量と経験値、最適なアドバイスで数多くの受験生を医学部合格に導いてきた、医学部予備校界屈指のカリスマ塾長。

