受験生におすすめの食べ物5選!食べるとよいものとNGなものを紹介
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:基礎知識

人生の一大イベントである受験。
多くの受験生が学習と向き合う日々を過ごしていますが、勉強ばかりに意識が向き、睡眠不足や不摂生などが続くことも。
しかし、体調管理を行い正しい食事を取ることは、パフォーマンスの向上につながる大切なことです。
そこで、受験生におすすめの食べ物を受験当日・前日に分けて紹介。
また、体調に影響を及ぼす可能性のあるNGな食べ物も挙げていきます。
いいコンディションで受験に挑めるよう、本記事を参考に生活を見直してみてください。
受験生におすすめの食べ物

甘いものを食べて眠くなってしまった経験はありませんか?
このように、食べ物は体調や集中力に大きな影響を与えます。
受験では、集中力だけでなく記憶力や判断力も必要です。
高いパフォーマンスを発揮するためには、まず食事の内容を見直すことが大切です。
そこで、受験や勉強中におすすめの食べ物を紹介します。
消化に良いもの
受験シーズンはどうしても緊張してしまいますよね。
緊張すると胃腸にストレスを与えやすく、自律神経の乱れにつながることも。
また、ストレスにより消化不良になりやすいため、腹痛や下痢、便秘などの症状が起こりやすくなります。
以下のような消化にいい食べ物を摂ることがおすすめです。
- 野菜:白菜、大根、キャベツ、にんじん、かぶ、だいこん、ほうれん草
- タンパク質:鶏むね肉、鮭、白身魚、豆腐、納豆、卵
- 炭水化物:うどん、おかゆ、そば、白米
- 果物:バナナ、りんご、ブドウ
- お菓子:ゼリー、プリン、蒸しパン
また、「煮る・蒸す・茹でる」の3つの加熱方法を取り入れることもおすすめです。
体を温められるもの
受験シーズンと呼ばれる1〜3月は1年の中でもとくに寒いシーズンです。
体が冷えると、めまい、だるさ、肩こりなどの不調をきたす可能性があります。
体を温める食べ物は以下のとおりです。
- 未精製の食材(黒糖、胚芽米など)
- 冬が旬の食材(にんじん、れんこん・ごぼう、ほうれん草など)
- 発酵食品(味噌、納豆など)
- お肉やお魚などのたんぱく質食材
- ビタミンEが豊富なナッツ類やアボカド
- 唐辛子、ショウガ、にんにく、玉ねぎなどのスパイス
紅茶やお茶などは温めてから飲むのもいいでしょう。
ビタミンB1を含むもの
長時間の勉強で疲れやすくなる受験期には、ビタミンB1の摂取が特に重要です。
ビタミンB1は糖質をエネルギーに変える代謝を助け、疲労回復や集中力の維持に欠かせない栄養素です。
食品では、豚肉、鶏肉、魚介類、大豆、全粒穀物、うなぎ、ひじきなどに多く含まれています。
効率よく摂るには、ビタミンB1の吸収を助けるビタミンB6やビタミンCを含む野菜や果物と組み合わせるのがおすすめです。
簡単な献立例としては、豚肉と野菜の炒め物、豆腐とわかめの味噌汁、玄米ご飯など、一食で手軽に摂れるメニューが効果的です。
摂りすぎは食欲不振や疲れやすさの原因になることもあるため、バランスを意識しましょう。
ブドウ糖を含むもの
はちみつやバナナといった甘みのある食べ物に含まれるブドウ糖は、脳の重要なエネルギー源です。
脳細胞は通常、血液中のブドウ糖をエネルギー源としており、適切な量を取り入れることが重要です。
ただし、ブドウ糖の過剰摂取は血糖値を上昇させ、肥満のリスクを伴います。
DHAを含むもの
DHAは、受験に必要な記憶力や判断力の向上に有効とされる成分が入っています。
DHAを含む食べ物は以下のとおりです。
- マグロやサバ、鮭、イワシなどの青魚
- イクラやすじこといった魚卵
- ウナギや筋子
魚系が苦手な人はサプリメントで代替も可能です。
勉強中におすすめのお菓子
受験勉強中は、集中力や記憶力を維持するために脳へのエネルギー補給が欠かせません。
手軽に食べられるお菓子をうまく取り入れることで、効率よく勉強を進めることができます。
特におすすめなのは、ブドウ糖を補給できるものや、少量で満足感があり消化に負担をかけないものです。
ゼリーやカステラ、チョコレート、ドライフルーツなどはその代表例です。
お菓子を選ぶ際は、量を適切にすること、糖分の質を意識すること、消化のしやすさを考えることがポイントです。
食べ過ぎると血糖値が急上昇して眠気や集中力の低下を招くことがあるため、適量を心がけましょう。
勉強の合間にこうしたお菓子を上手に取り入れることで、脳を活性化させながら効率的に学習を進められます。
鉄分を含むもの
鉄分は、血液中の赤血球の材料となる栄養素です。
鉄分を摂ることで、脳に酸素を十分に供給し、集中力を高めることができます。
鉄分を多く含む食べ物は、レバー、カツオ、小松菜、赤身肉などです。
タンニンを含む飲み物(コーヒーや紅茶など)は鉄分の吸収を妨げるため、摂取タイミングに注意しましょう。
受験生の体調管理に役立つ食事計画
受験期は、勉強だけでなく体調管理も合格への大きなカギです。
日頃からバランスの取れた食生活を意識することで、集中力や記憶力を維持し、体調不良を防ぐことができます。
特に受験前日や当日の食事は、胃腸に負担をかけず、脳に十分なエネルギーを届け、精神的な安定を保つことが重要です。
基本のポイントは、消化の良さ・栄養バランス・手軽さの三つです。炭水化物で脳のエネルギーを補給し、たんぱく質で体の回復を助け、野菜や果物でビタミン・ミネラルを摂ることが理想です。
受験前日には、脂っこい食事や刺激物を避け、消化に優しいメニューを選ぶと安心です。
当日は朝食をしっかり取り、脳の働きをサポートしつつ、緊張で食欲がない場合はゼリーやバナナなど手軽にエネルギーを補給できるものを活用します。
さらに、体調不良時には無理に食べず、消化の良いスープやおかゆなどで栄養を補いながら体を休めることが大切です。
こうした工夫を取り入れた食事計画により、受験期を通して体調を崩さず、集中力を維持しながら学習を進めることができます。
受験生におすすめの献立例
受験期は、脳の働きを支え、疲労を回復するために、栄養バランスの良い食事が欠かせません。
朝食・昼食・夕食それぞれで、消化に優しく体を温める食材や、ビタミンB1、DHA、鉄分を効率的に摂れる組み合わせを意識すると、集中力や体調の維持に役立ちます。
朝食には、炭水化物を主食に、卵料理や豆腐・わかめ入りの味噌汁、ほうれん草のおひたしなどを組み合わせると、脳のエネルギーをしっかり補給できます。
昼食には、鶏そぼろ丼や焼き鮭の親子丼と、具だくさんの味噌汁やサラダを組み合わせると、午後の勉強も効率よく進められます。
鶏そぼろなどはまとめて作り置きしておくと時短にもなります。
夕食には、魚の塩焼きや野菜の煮物、きんぴらごぼう、雑穀入りご飯などを組み合わせると、DHAや鉄分を効率的に摂取でき、疲労回復や体調管理に効果的です。
魚はオーブントースターで簡単に焼け、煮物は前日に下ごしらえしておくと便利です。
これらの献立を意識することで、受験期でも体調を崩さず、脳と体をしっかりサポートしながら学習に集中することができます。
受験生にNGな食べ物
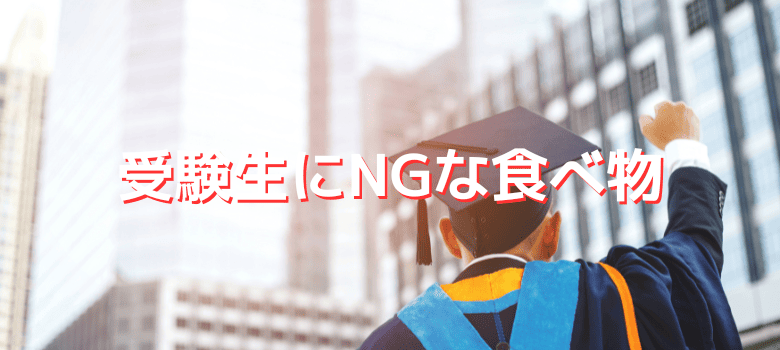
先ほどは受験生におすすめの食べ物を紹介しました。
受験に向けてコンディションをよくしていくのは大切ですが、コンディションを悪化させる食べ物を避けることも大切です。
そこで、受験生にNGな食べ物を紹介します。
消化の悪いもの
受験前日は、消化の悪いものは控えましょう。
消化の悪い食べ物を摂取すると、胃にとどまる時間が長くなり、胃に負担がかかる可能性があります。
その結果、胃もたれや気持ち悪さを催すこともあります。
消化の悪い食べ物には脂肪や食物繊維の多い食材、具体的にはごぼう、きのこ、れんこんなどが挙げられます。
これらをどうしても食べたい場合は、調理方法や食材選びを工夫することで、胃への負担を軽減できます。
たとえば、食材をよく加熱することは有効です。
蒸す、煮る、または炒めることで、食物の繊維がほぐれ、生の状態よりも消化しやすくなります。
食材を細かく刻むことも有効です。
辛いもの
個人差はありますが、辛いものを食べすぎると不調をきたす可能性があります。
辛い食べ物に含まれる唐辛子の辛みとなる成分カプサイシンは、過剰摂取することで粘膜が傷つきやすくなり、喉や胃が荒れることがあります。
胃に刺激を与えることで、消化の時間もかかってしまうデメリットもあります。
一方で、辛いものを食べることで爽快感を得られるといった人もなかにはいるでしょう。
どうしても食べたいという人は、自身の体調や受験時期を考慮したうえで、考えてみてください。
生もの
牡蠣などの生ものに当たった経験をした人はいるのではないでしょうか。
生魚や生肉には、細菌や寄生虫による食中毒のリスクが潜んでおり、早い人は食後30分から4時間で腹痛、下痢、嘔吐といった症状が起こります。
腸管出血性大腸菌やカンピロバクターなど、さまざまな食中毒の種類がありますが、菌の潜伏期間は大体24〜48時間です。
カンピロバクターでは、2〜7日を要します。
そのため、回復までに2日以上かかることは珍しくありません。
もしその期間に受験があり無理に試験を受けたとしても、会場のトイレなどで感染が広がる可能性もあるので。
そのため、一般的には自宅療養が勧められています。
ゲン担ぎにおすすめの食べ物
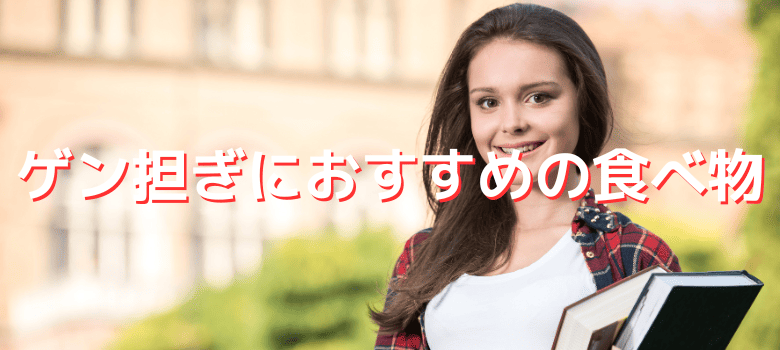
日本では必勝を願ってトンカツを食べる風習があります。
このように、大切な試験や本番がある前日には、運気を上げるためにゲン担ぎとされる食べ物が食卓に並ぶことは珍しくありません。
受験前日と当日に食べるとよいゲン担ぎの食べ物を紹介します。
受験前日
受験前日におすすめのゲン担ぎの食べ物は以下のとおりです。
- カツ=>勝つ
- れんこん=試験にとおる(穴が貫通していることから)
- タコ=多幸、オクトパス(置くとパス)
- 西京焼き=最強
受験当日
受験当日におすすめのゲン担ぎの食べ物は以下のとおりです。
- おむすび=いい結果を結びつける
- おくら=五角(合格)
- こんぶ=喜ぶ
- いよかん=いい予感
- 納豆=ネバネバ(最後まで粘り強く)
受験生への差し入れ・プレゼント
受験生を応援する家族や友人、先生が贈る差し入れやプレゼントは、栄養補給やリフレッシュ、ゲン担ぎなど、目的に合わせて選ぶことが大切です。
栄養補給には、手軽にエネルギーを補える栄養ドリンクや、少量で満足できる個包装のお菓子が適しています。
集中力や疲労回復をサポートできるため、勉強の合間にぴったりです。
リフレッシュ目的なら、温かい飲み物や香りの良いお茶など、気分を落ち着けるアイテムがおすすめです。
また、ゲン担ぎや縁起を意識するなら、五角形の最中やだるまモチーフのお菓子など、受験にちなんだ縁起物を選ぶのも喜ばれます。
贈る際は、アレルギーの有無、日持ち、持ち運びやすさに注意しましょう。
長時間の移動や試験会場での保管にも配慮し、手軽に食べられるものを選ぶと安心です。
こうしたポイントを押さえて差し入れやプレゼントを選ぶことで、受験生にエネルギーと気持ちのサポートを届けることができます。
コンビニで買える受験生向け食事
受験期は、勉強や移動で時間が限られることも多く、自宅以外で手軽に食事を摂る必要がある場合もあります。
そんなときに便利なのが、コンビニで手に入る栄養バランスの良い食事や軽食です。
おすすめは、脳のエネルギー源となる炭水化物と、たんぱく質やビタミン・ミネラルをバランスよく摂れる商品です。
具体的には、おにぎりやサンドイッチ、サラダチキン、ヨーグルト、ゼリー飲料などが手軽で消化にも優しく、集中力を維持するのに役立ちます。
選ぶ際は、消化に負担がかからないものを選ぶこと、糖質・たんぱく質・ビタミンをバランス良く組み合わせること、そして持ち運びやすさや温度管理にも配慮することがポイントです。
集中力を上げるためのコツ
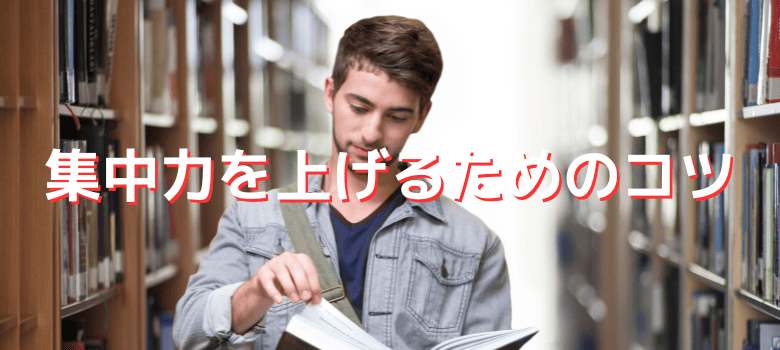
試験では、限られた時間で問題を解かなければならず、いかに集中力をもって試験に挑めるかが重要です。
そこで、集中力を上げるコツを伝授します。
バランスのよい食事を心掛ける
栄養バランスの整った食事は、脳と体を正常に動かすために不可欠です。
とくに、脳を活性化させるタンパク質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなどの栄養素を摂るようにしましょう。
一方で、揚げ物や添加物の多い食品、辛いものは消化に負担をかけてしまいます。
前項でも紹介した「受験生にNGな食べ物」で挙げたものは避けましょう。
朝食を取る
朝時間がないことから朝食を抜いて学校や塾に行ってしまった人はいませんか。
実は、朝食には受験に効果的なパワーが多く含まれています。
文部科学省の調査では、毎日朝食をとる児童生徒ほど、学力調査の得点が高い傾向があるという結果が報告されました。
朝食を抜くと血糖値が不安定になり、脳をはじめとする体のいろいろな働きが低下してしまいます。
とくに優先順位が低くされがちな朝食ですが、よい1日のスタートを切るためにも、意識的に取り入れるようにしましょう。
ちょうどよい食事量を心掛ける
多く食事を摂り過ぎてしまったとき、眠くなってしまうことがあります。
過剰な食事量だと、消化器官が食べ物を消化しようと血液を必要とするため、脳への血液供給が減少してしまうのです。
また、食事をする際はよく噛むことを意識しましょう。
噛むことで唾液の分泌が促され、栄養の吸収が促進されるだけでなく、満腹中枢も刺激されます。
お腹に負担がかからないようにする
消化のよくない食べ物を多く摂ると、消化器官に負担をかけてしまいます。
それにより、血液が消化器官に集中し、脳に送られる血液が減少して集中力の低下につながります。
炭酸飲料は胃にガスを溜め込み、不快感を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
十分な睡眠を取る
睡眠不足は心身ともに悪影響を及ぼします。
6時間の睡眠を2週間続けると、集中力が酩酊状態に近づくという結果も報告されています。
適切な睡眠時間を確保し、日中どうしても眠い場合は、15〜20分ほどの仮眠をとるようにしましょう。
カフェインの摂りすぎに気を付ける
カフェインは適量であれば集中力を高める効果がありますが、摂りすぎると不安感や神経過敏につながる可能性があります。
また、腹痛や下痢、利尿作用などのリスクもあります。
適切な量を守り、健康的に集中力を高めましょう。
眠気覚ましに効果的な食べ物・飲み物
勉強中の眠気を効果的に覚ますためには、カフェインだけに頼らず、食べ物や飲み物の工夫を取り入れることが有効です。
例えば、ミントや柑橘系の香りは脳を刺激して目を覚ましやすくする効果があります。
また、血糖値を穏やかに上げる軽食や、咀嚼を促すガムやナッツなども眠気対策としておすすめです。
それぞれのメリット・デメリットを理解しておくことも重要です。
ミントや柑橘系の香りは手軽にリフレッシュできますが、香りに慣れると効果が薄れることがあります。
血糖値を上げる軽食は集中力維持に役立ちますが、糖分の取りすぎは眠気やだるさを招く場合があります。
咀嚼を促す食品は、口の運動で眠気を抑えやすい一方、食べ過ぎると消化に負担がかかることもあります。
摂取タイミングもポイントです。
眠気を感じる前や、勉強の合間に少量ずつ取り入れると効果的です。
過剰に摂取すると、胃もたれや頭痛、集中力の低下など体調不良を引き起こすことがあるため注意が必要です。
集中力を高める即効性のある食べ物
試験直前や勉強中に集中力が途切れたときには、即効性のある食べ物や飲み物を取り入れることで、脳を素早く活性化させることができます。
特に効果的なのは、ブドウ糖を素早く補給できるものです。
ブドウ糖タブレットやラムネ、はちみつレモンなどは、短時間でエネルギーを補給でき、集中力の回復に役立ちます。
また、カフェインを適量含む飲み物(コーヒーや緑茶など)も脳を覚醒させ、注意力を高める効果があります。
ただし、摂りすぎると心拍数の増加や不安感を招くことがあるため、量とタイミングには注意が必要です。
さらに、咀嚼によって脳を刺激する食品も集中力維持に効果的です。
ガムやするめなどは、噛む動作が脳への血流を促進し、眠気やだるさを抑える働きがあります。
摂取のタイミングとしては、眠気や集中力の低下を感じた直後、あるいは勉強や試験の合間に少量ずつ取り入れるのが最適です。
まとめ

受験シーズンで不安に感じていた人は、本記事を読んで少しでも安心していただけたら嬉しいです。
適切な食事を取り、健康的な生活を送り、当日に挑みましょう。
大阪のおすすめ医学部予備校13選では、医学部予備校に関する情報のほかにも、本記事のようなお役立ちコラムを掲載しています。
ぜひ参考にしてみてください。
この記事の執筆者:医進の会代表 谷本秀樹

大学入試は四谷学院などの大手予備校や多くの医学部受験予備校で、主に生物の集団授業と個別授業で300人以上の受験生を担当。
自身の予備校『医進の会』発足後は、これまで500人以上の生徒の受験と進路指導に携わってきた。
『個別の会』の代表でもあり、圧倒的な医学部入試情報量と経験値、最適なアドバイスで数多くの受験生を医学部合格に導いてきた、医学部予備校界屈指のカリスマ塾長。

