2025年版|医学部学士編入試験制度とは?合格するための方法や実施大学、流れや注意点を解説
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:社会人・編入

「社会人からでも医師を目指せる?」「医学部学士編入制度ってどんな制度?」「編入試験を突破するための対策が知りたい」と考えている方もいるでしょう。
本記事では、医学部学士編入を実施している大学、制度の特徴やメリット・デメリット、編入試験内容や試験対策について解説していきます。
医学部学士編入試験制度について知りたい方や、社会人から医師を目指している方は、ぜひ最後までお読みください。
- 医学部学士編入の特徴
- 医学部学士編入の対策方法
- 医学部学士編入を実施している大学
目次
医学部学士編入制度とは

医学部編入とは、4年制もしくは6年制大学を卒業してすでに学士資格を取得している社会人が、医学部に編入できる制度を指します。
主に4年制大学を卒業し、学士の学位を持っている方が編入対象となります。
しかし、学士編入制度を採用している大学の中には、短大卒や4年制大学に2年以上在学していたと証明できる方も対象とする場合があるのが特徴です。
一般入試とは異なり、6年間の課程の途中から編入できるのが特徴です。
2020年には全国82校の中で、主に地方の国公立大学を中心とした31校が学士編入試験を導入しました。
大学受験時に医学部を目指していたが断念した方や、そもそも医学部を考えていなかった方にも、医師として働けるチャンスを提供する制度です。
制度の成り立ち
医学部編入は、どのような経緯で作られたのでしょうか。
この制度は、1975年に大阪の医学部が全国に先駆けて実施したことが始まりとされています。
2000年頃、文科省によって、大学卒業後に社会人経験を積んだ方の医学部編入を推進する取り組みが始まりました。
良医育成を目的としたこの活動によって、各大学も次々と編入制度を取り入れていきました。
日本で医師を目指すための一般的な方法は、高校卒業後すぐに医学部に入学し、医学教育を受けるコースです。
高校卒業後すぐに医学の道へ進むと、現役の医師として働ける年数が長くなり、経験を積むメリットが期待できます。
一方、アメリカで主流となっているのは、4年制大学を卒業後にメディカルスクールへ入学して医学教育を受けるスタイルです。
医師免許を取得する前に、医学だけでなくさまざまな学問を学び、人としての成熟度を高めてから医師になることができるのが大きなメリットです。
今日の日本における医学部編入制度は、日本の医学教育システムにアメリカ式のメリット部分を取り入れたものといえるでしょう。
学士取得を前提としない編入も
多くの医学部編入試験では「学士号を取得、または取得見込み」であることが応募条件とされています。しかし、大学によっては学士を持たない場合でも出願可能なケースがあります。具体的には、4年制大学に2年以上在籍し、指定の単位を取得した学生、短期大学卒業者、高等専門学校(高専)卒業者などが対象となる大学も存在します。
また、医学部編入試験には年齢制限が設けられていないのが一般的で、社会人経験を経て受験する方も多く見られます。そのため、現役学生とは異なる実務経験、論理的思考力、問題解決力などが評価される場合があります。
さらに、出願資格として TOEIC や TOEFL などの英語資格のスコア提出を求める大学もあります。目安としてはTOEICでは700〜800点程度、TOEFL iBTでは80〜90程度が一般的ですが、大学ごとに基準が異なるため、志望校の募集要項を必ず確認しておきましょう。
医学部学士編入試験の流れ・準備

医学部編入試験の流れについて解説します。
現在国公立大学27校と私立大学3校で合計30大学が実施しており、入学時期や試験制度が変更される可能性があるため、各大学の募集要項をチェックしておきましょう。
STEP1:書類審査
STEP1は書類審査です。
書類審査だけで合否を決める大学は年々少なくなってきていますが、書類で合格になることで学科試験の倍率が緩やかになるため、書類審査のある大学は有力な選択肢といえるでしょう。
STEP2:学科試験
STEP2は学科試験です。
医学部編入の学科試験では、英語と生命科学が最も難易度の高い中心科目です。英語は医学系論文の読解が中心で専門語彙や論理展開の理解が求められ、生命科学は細胞・生化学・生理学など範囲が広く、体系的な知識整理が不可欠です。大学によっては数学・化学・物理が課される場合もあり、理系出身者には有利に働きますが、文系出身者にとっては学習負担が大きくなるなど、科目選択には明確なメリット・デメリットがあります。得意分野を生かせる大学を選ぶのか、必要科目の負担を最小限にするのかは、受験戦略に直結します。
また、大学ごとに出題形式や重点分野が大きく異なるため、過去問の活用は必須です。実際に解いてみて頻出分野や時間配分の癖を把握し、弱点が知識不足なのか理解不足なのかを整理することで、科目ごとの優先順位が明確になります。効率的な学習計画を立てるには、まず主要科目に重点的に時間を割きつつ、過去問から逆算して学習範囲を絞り、週単位で達成度を確認しながら計画を微調整することが大切です。こうした戦略的な積み上げが、限られた時間で合格を目指す最短ルートとなります。
STEP3:面接(集団討論)
STEP3は面接です。
面接は学士編入試験の中でも重要視されるポイントです。
面接の方式は個人面接が課されることもあれば、集団討論が行われる大学もあるため、調べて対策するようにしましょう。
医学部学士編入のメリット

ここでは、医学部学士編入のメリットについて詳しく紹介します。
メリットはこちらの点が挙げられます。
- 受験科目が少ない
- 国公立大学も併願可
- 専門課程から学べる
- 文系出身でも受験可能
受験科目が少ない
編入試験は、学校によっては生命科学と英語の2科目で受験可能です。
私立大学の医学部を一般試験で受験する場合、数学、英語、理科の2科目が必須とされます。
国立大学医学部を一般入試で受験する場合、共通テストがあるため、さらに多くの科目の勉強が必要になります。
既に学士を有する人にとって、共通テストは未経験の分野であるため、改めて勉強する際にはしっかりと取り組む必要があります。
一方、学士編入試験は科目が少ないため、大学生なら卒業後の受験を見据えて学校の勉強と並行して学習できますし、社会人でも働きながら勉強することが可能です。
国公立大学も併願可
国公立の一般入試では、前期と後期でそれぞれ一つの大学しか受験できません。
しかし、学士編入の場合は大学ごとに独自の日程で試験が行われるため、各大学の日程次第で併願も可能です。
一人の受験生が複数の学校を受験することができるため、入学辞退による追加合格も発生し得ます。
例えば、非常に高い倍率であっても、実際にはもっと低い場合もあります。
学士編入を本気で目指す場合は、あらかじめ各大学の入試日程を調べ、複数の学校への出願を積極的に検討しましょう。
専門課程から学べる
学士編入制度は、大学の3年次もしくは2年次に編入して専門課程から学べる制度です。
通常、大学の最初の1〜2年は一般教育課程とされており、専門的な授業が行われることは少ないです。
そのため、既に一般教育課程を修了している学生であれば、いきなり専門課程から編入しても問題ないと考えられています。
文系出身でも受験可能
医学部と聞くと理系のイメージがありますが、実は文系出身でも十分合格を目指せます。
大学によって試験科目は異なるため、自分の得意な科目で勝負できる大学を選びましょう。
特に英語はどの大学でも必須の重要科目であるため、国際教養学部や英文学部出身の方には有利と言えます。
医学部学士編入を実施している大学

医学部編入実施大学について解説します。
医学部学士編入を実施している国公立大学
国公立大学で実施されている医学部学士編入について、各大学の一覧と出願時期、筆記試験日程をまとめて解説します。なお、入試情報は毎年変更される可能性があるため、
最新の内容は必ず各大学が公開する募集要項で確認してください。
| 大学名 | 出願時期 | 筆記試験の日程 |
|---|---|---|
| 旭川医科大学 | 2025年9月1日(月)〜9月5日(金) | 2025年10月25日(土) |
| 北海道大学 | 2025年7月15日(火)〜7月24日(水)(17時まで必着) | 2025年8月17日(日) |
| 弘前大学 | 2025年10月21日(火)〜2025年10月27日(月)(17時まで必着) | 2025年11月16日(日) |
| 秋田大学 | 2025年9月4日(木)〜9月12日(金)(17時まで必着) | 2025年11月6日(木)・7日(金) |
| 筑波大学 | 2025年6月2日(月)〜6月6日(金)必着 | 2025年7月12日(土)・13日(日) |
| 群馬大学 | 2025年7月23日(水)〜7月28日(月) | 2025年9月7日(日) |
| 東京科学大学 | 2025年5月12日(月)〜5月16日(金)(15時まで) | 2025年6月11日(水) |
| 富山大学 | 2025年7月28日(月)〜8月1日(金)(17時まで) | 2025年9月7日(日) |
| 金沢大学 | 2025年8月18日(月)〜8月22日(金) | 2025年9月19日(金) |
| 福井大学 | 2025年7月7日(月)〜7月11日(金)(16時必着) | 2025年8月30日(土) |
| 浜松医科大学 | 2025年7月28日(月)〜8月6日(水)(17時まで必着) | 2025年8月30日(土) |
| 名古屋大学 | 2025年5月1日(木)〜5月9日(金)(16時必着) | 2025年6月5日(木) |
| 滋賀医科大学 | 2025年8月25日(月)〜8月29日(金)(17時必着) | 2025年9月20日(土) |
| 大阪大学 | 2025年6月2日(月)〜6月6日(金) | 2025年7月5日(土) |
| 神戸大学 | 2025年7月3日(木)〜7月9日(水) | 2025年8月5日(火) |
| 奈良県立医科大学 | 2025年12月2日(火)〜12月6日(日) | 2026年2月1日(日) |
| 岡山大学 | 2025年4月9日(水)〜4月18日(金)(17時必着) | 2025年6月28日(土) |
| 島根大学 | 2025年7月15日(火)〜7月18日(金)(17時必着) | 2025年8月23日(土) |
| 鳥取大学 | 2025年8月4日(月)〜8月8日(金) | 2025年9月6日(土) |
| 山口大学 | 2025年7月28日(月)〜7月31日(木)(17時必着) | 2025年9月28日(日) |
| 愛媛大学 | 2025年6月23日(月)〜6月27日(金)(消印有効) | 2025年7月19日(土) |
| 香川大学 | 2025年5月7日(水)〜5月16日(金)(17時必着) | 2025年6月7日(土) |
| 高知大学 | 2025年6月9日(月)〜6月12日(木)(17時必着) | 2025年7月5日(土) |
| 長崎大学 | 2025年7月11日(金)〜7月18日(金)(17時必着) | 2025年8月22日(金) |
| 大分大学 | 2025年4月21日(月)〜4月25日(金)(17時必着) | 2025年6月17日(火) |
| 鹿児島大学 | 2025年5月2日(金)〜5月9日(金)(17時必着) | 2025年6月7日(土) |
| 琉球大学 | 2025年7月31日(木)〜8月7日(木)(17時必着) | 2025年9月9日(火) |
医学部学士編入を実施している私立大学
私立大学で医学部学士編入を実施している大学と出願時期、筆記試験の日程について解説します。なお、最新情報は各大学の募集要項をご確認ください。
| 大学名 | 出願時期 | 筆記試験の日程 |
|---|---|---|
| 東海大学 | 2025年10月10日(金)〜10月22日(水)(必着) | 2025年11月9日(日) |
| 北里大学 | 2025年11月1日(土)〜11月6日(木)(当日消印有効) | 2025年11月16日(日) |
| 獨協大学 | 2025年9月1日(月)〜9月19日(金)(必着) | 2025年10月4日(土) |
| 岩手医科大学 | 2026年1月19日(月)〜2月5日(木)(必着) | 2026年2月16日(月) |
| 金沢医科大学 | 2025年11月10日(月)〜11月15日(土)(必着) | 2025年11月22日(土) |
| 久留米大学 | 2025年9月22日(月)〜10月3日(金)(必着) | 2025年11月15日(土) |
| 東京医科大学 | 2025年10月20日(月)〜10月31日(金)(必着) | 2025年11月29日(土) |
医学部学士編入の試験内容
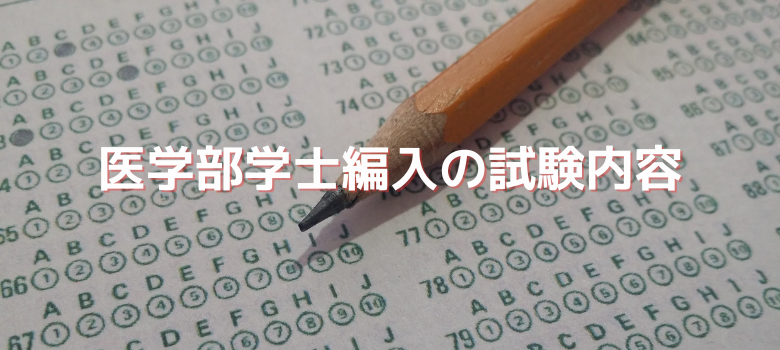
医学部編入試験では、どのような内容の試験が行われるのでしょうか。
ここでは、試験内容について詳しく紹介していきます。
選考時期
医学部学士編入試験の選考時期は、医学部の一般入試と異なるのが特徴です。
学士編入試験の時期は大学によって異なりますが、7〜11月に試験を実施する学校が多い傾向にあります。
学士編入の出願時期は、試験日の3か月前など早めになっています。
出願を検討している場合、あらかじめ大学の公式ホームページで確認しておくとよいでしょう。
入試日程が重なっていない場合は、複数の学校を受験できるため、合格率を高めるためにも複数の大学を併願するのが望ましいです。
筆記試験
筆記試験で重要な科目は、英語と生命科学です。
大学によってはそれに加え、化学や物理、数学も実施するケースがあります。
また、一次試験あるいは二次試験で小論文を実施している大学も多いため、受験予定の大学の試験内容をしっかり確認しておきましょう。
英語の難易度が非常に高い
医学部では解剖学、生理学、生化学、薬理学などの専門用語を英語で理解する力が求められ、高校レベルの参考書だけでは十分ではありません。編入試験の英語は、①専門用語の膨大さ(解剖用語・疾患名・検査名など)、②論文独特の構文・論理展開(IMRAD形式)、③生命科学内容の英語読解、④情報量の多さによる速読力が必要です。
対策としては、まず『Gray’s Anatomy』や『Netter』など主要テキスト由来の医学英語を体系的に暗記し、QuizletやAnkiで毎日反復します。次に、PubMedのshort communicationやreviewのAbstractを毎日読み、専門語彙リストを作成して確認します。速読力はAbstract→Conclusion→Methodsの順に読むスキミングで鍛え、文章構造を意識して骨格だけを素早く把握する練習が効果的です。また、TOEFLやTOEICを活用して英語力の基礎を固め、出願条件を満たすと同時に論文読解力を底上げします。最後に過去問を通して論文形式の長文+専門語彙穴埋め問題に慣れ、語彙力・速読力・要約力を磨くことで実戦力を養います。
医学部で学ぶ分野の出題
医学部編入試験では、生命科学(生物学・分子生物学・生化学・生理学)が主要科目として出題され、基礎医学レベルの理解が求められます。生物学では細胞構造・細胞周期・遺伝・代謝などを理解し、細胞レベルでの反応を論理的に説明できる力が重要です。分子生物学ではDNA・RNA・タンパク質の構造と機能、遺伝子発現、転写・翻訳、シグナル伝達が頻出です。生化学は代謝経路や酵素反応、ホルモン調節、図表問題が中心で、生理学では神経・筋・循環・呼吸・腎の機能や恒常性のフィードバック機構の理解が不可欠です。
学習の基本は、一般生物→分子生物→生化学→生理学の順で理解を積み上げ、図や経路で仕組みの流れを把握することです。志望校の過去問を確認し、出題傾向に合わせた分野別優先順位をつけることも重要です。参考書は、図解が多く体系的にまとめられ、問題演習付きのものを選ぶと理解が定着しやすく、範囲が広いため独学が難しい場合は、予備校で解説講義や過去問演習を活用すると効率的に学習できます。
面接
一般入試と学士編入の面接を比較すると、学力ややる気はもちろん、人柄も問われます。
一般入試の面接では、倫理観や最低限のコミュニケーション能力があるかどうかがチェックされます。
一方、学士編入試験の面接では「大学の求める人材にどれだけマッチしているか」「なぜ進路を変えてまで医学部を目指しているのか」「大学生活や社会人経験で得た能力をどのように医学分野に活かすのか」といった点が重点的に質問されます。
就職活動の面接と似ている点があり、もし一次試験の成績が同等であれば、大学の求める人材にマッチしている方が合格する可能性が高くなるでしょう。
圧迫面接があることも
また、編入試験の場合、圧迫面接を行う大学も少なくありません。
これは受験者のやる気やストレス耐性を見抜くためだと言われています。
「最初は他の学部に進学したのだから、そこまで医師になりたいと思っていないのでは?」「現役の高校生を合格させれば、若い人材を育てられる」といった態度を取られることもあります。
面接官の態度に物おじせず、自分の意見をしっかりと伝えられるよう練習しておきましょう。
集団討論が行われる大学もある
さらに、学士編入試験では集団討論を実施する学校もあります。
面接対策はもちろん、集団討論がある学校ではその対策も必要です。
模擬面接や集団討論の練習は予備校に依頼するのがおすすめです。
予備校は各大学の面接試験の傾向を熟知しているため、効率的に対策を進めることができます。
医学部編入試験で合格するために
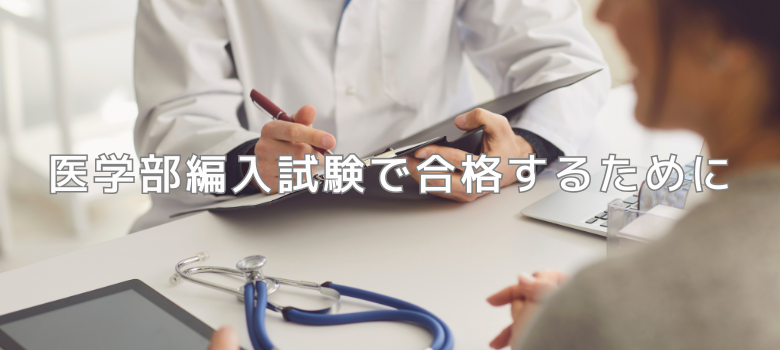
医学部編入試験に合格するためには、どのような点に気をつけるべきでしょうか。
ここでは、合格を勝ち取るためのポイントについて詳しく説明していきます。
志望校の情報収集を欠かさない
先述のとおり、医学部編入試験は試験日が重ならなければ複数の学校へ出願できるため、各大学の試験日はもちろん、受験科目などの情報収集をしっかりと行う必要があります。
自分ひとりでは情報収集に不安がある方は、予備校を活用するのがおすすめです。
予備校では、学校に関する情報や過去問などを手軽に入手できるため、効率的に受験戦略を立てられます。
計画的に準備する
医学部編入に挑戦する場合、計画的に準備を進める必要があります。
計画を立てずに挑戦すると、失敗するリスクが高まります。
準備は、これまでの基礎学力だけでなく、日々の勉強にどのくらいの時間を確保できるかによって異なります。
試験日から逆算して、何をいつまでに準備するべきかを整理し、時間に余裕をもって準備を進めましょう。
スケジュール管理を徹底する
仕事と並行しながら学士編入を目指す場合、タイムマネジメントを徹底する必要があります。
特に社会人は多忙なため、スケジュール管理をしっかり行わないと、準備期間でつまずいたり、万全の状態で試験に臨めなかったりする可能性があります。
体調や仕事のスケジュールを考慮しながら、無理のない勉強計画を立てましょう。
予期せぬ事態も想定し、1日にどれだけ進められるか、現実的かつ具体的な目標設定を行うことが重要です。
学士編入志望者には、社会人経験を積んできたという大きな強みがあります。
年齢を重ねた分、管理能力も高くなっているはずです。
医学部予備校に通う
予備校に通い、プロの指導を受けながら自分に合ったスケジュールで学習を進めることは、医学部編入の合格に大きく役立ちます。医学部編入では英語・生命科学ともに大学レベルの理解が求められますが、これらを体系的に網羅した市販テキストはほとんどありません。そのため、独学では「何をどこまで勉強すべきか」が分かりにくく、効率が落ちることが多いのが現状です。
専門予備校では、大学ごとの出題傾向を踏まえたオリジナル教材や個別指導を受けられ、弱点の発見や知識の整理がスムーズになります。また、面接・小論文・集団討論といった二次試験の実践的な対策、最新の入試情報の提供など、独学では得られないサポートも充実しています。こうした指導のもとで勉強すれば、無駄のない学習が可能になります。
特に社会人にとっては、学習管理やメンタル面の支援を受けられることが大きなメリットです。限られた時間で学習を進める必要がある社会人でも、予備校のサポートを活用することで迷いが減り、安定したペースで合格まで走り切ることができます。
失敗しない医学部予備校の選び方や、大阪で体験授業を受けられる予備校についてもこちらで紹介しています。
医学部学士編入試験対策をするなら医進の会

医進の会では学士編入試験対策を実施しています。
面接対策も入念に実施しており、一人ひとり最適なカリキュラムで医学部受験対策をしています。
編入試験は志望校に対して最適なカリキュラムで学習をすることが大切です。
医進の会では志望校の傾向に合わせた筆記試験、面接対策を行っており、学士編入試験に合格できる対策を行っています。
無料の体験授業・面談はこちら無料電話問い合わせ
06-6776-2934
一般入試と編入試験どちらを選ぶべきか
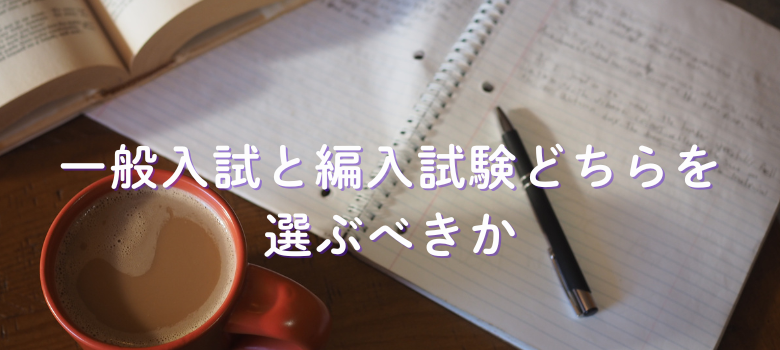
編入試験を検討している方は一般入試とどちらを選ぶのが良いか考えている方もいるのではないでしょうか。
ここでは一般入試と編入試験でどちらを選ぶべきか解説します。
両方対策するのは効率が良くない
まず両方対策するという選択肢は避けるようにしましょう。
両方対策しようとすると科目数が多くなるため、かえって合格が遠のきます。
志望校の過去問を確認し、一般入試が受かりやすいか、編入試験のほうが合格しやすいか予め決めておくようにしましょう。
私立大学医学部は一般入試がおすすめ
私立大学医学部は編入試験を実施している大学が少ないため、一般入試を選択するようにしましょう。
私立大学医学部受験でおすすめの受験方法は、複数の私立大学医学部を併願して受験することです。
国公立大学医学部は科目によって決める
国公立大学医学部は得意科目によって判断するようにしましょう。
国公立大学医学部の一般入試では数学、英語、理科2科目と、共通テストで85%前後の得点が必要なため、幅広い科目で高いレベルが求められます。
編入試験では科目数が少ないため対策しやすい側面がある一方で、生命科学の対策が難しい点が挙げられます。
独学で生命科学の対策をするのは難しいため、編入試験を選択する場合は医学部予備校などに入塾し、専門的な対策を行うようにしましょう。
医学部学士編入が向かない人・やめるべき人
医学部編入には大きなメリットがある一方で、「やめておいた方がいい」と言われる理由も存在します。競争率は多くの大学で10〜20倍を超え、限られた枠を争う厳しい試験です。また、生命科学・英語の学習量は想像以上に多く、数ヶ月では合格レベルに到達しにくいため、長期的な計画が欠かせません。さらに、受験料・参考書・予備校費用など経済的な負担も小さくなく、社会人の場合は仕事との両立による精神的プレッシャーも大きくなります。
特に「学習時間がほとんど取れない」「独学でコツコツ積み上げるのが苦手」「高い競争率に強いストレスを感じる」といった方は、編入より一般入試の再挑戦や他学部進学を検討したほうが良い場合もあります。
編入は魅力的な選択肢ですが、現実的な負担や難易度を踏まえたうえで、自分に合ったルートを見極めることが重要です。
まとめ

医学部学士編入制度は、年齢制限が設けられていない場合が多く、社会人としての経験を積んだ後でも医師を目指すことができます。
しかし、全国的に制度を導入している大学が少なく、倍率も高いため、入学を勝ち取るのは容易ではありません。
社会人は多忙なため、独学では十分な試験対策を行うのが難しい場合があります。
そのような方は、医学部編入専門の予備校を検討するとよいでしょう。
大阪のおすすめ医学部予備校13選を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事の執筆者:医進の会代表 谷本秀樹

大学入試は四谷学院などの大手予備校や多くの医学部受験予備校で、主に生物の集団授業と個別授業で300人以上の受験生を担当。
自身の予備校『医進の会』発足後は、これまで500人以上の生徒の受験と進路指導に携わってきた。
圧倒的な医学部入試情報量と経験値、最適なアドバイスで数多くの受験生を医学部合格に導いてきた、医学部予備校界屈指のカリスマ塾長。

