オススメの休憩サイクルとは?受験勉強の休息の重要性や効果的な取り方を徹底解説!
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:基礎知識
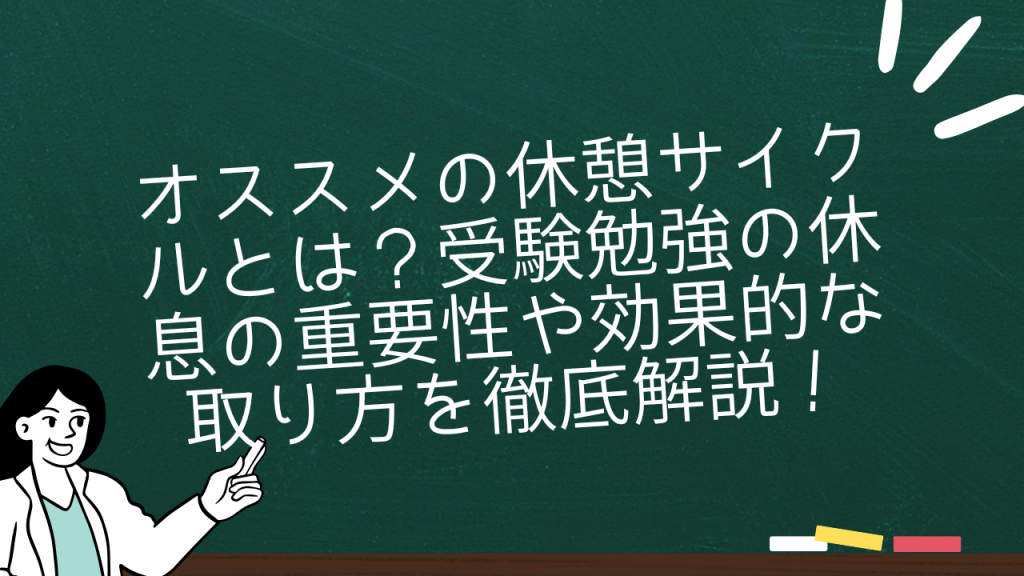
長時間集中して勉強を続けると、脳は疲労し、記憶力や理解力が低下します。
その結果、勉強の効率や成果が落ちてしまいます。
そこで、勉強の効率を上げるためには、適切な休憩をとることが大切です。
この記事では、休憩の取り方や具体的な方法などを解説します。
勉強効率をアップさせるために、休憩の取り方の参考にしてください。
勉強の休憩の重要性と効果的な取り方
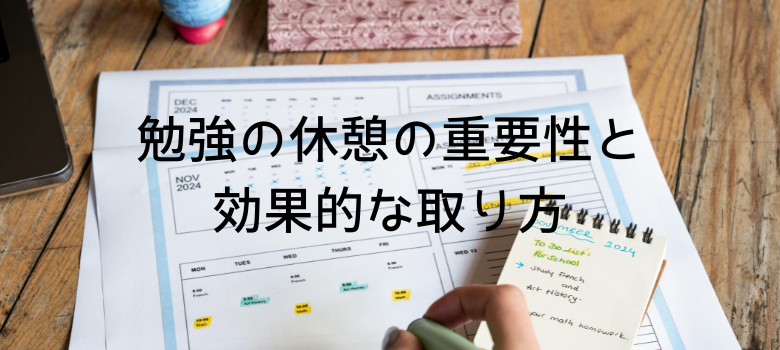
勉強はエネルギーを消費するものであり、適宜、休憩を入れるべきです。
まずは勉強の休憩について重要性と効果的な取り方を
休憩なしの勉強は非効率
人間の集中力には限界があります。
一般的には、大人でも45分程度が集中できる平均時間と言われています。
受験生はもっと短い時間で集中力が切れてしまう場合もあります。
集中力が切れた状態で勉強を続けても、脳は情報を十分に吸収できません。
また、疲労やストレスがたまり、勉強への興味や意欲が低下してしまいます。
そのため、休憩なしで勉強することは非効率であり、逆効果になる可能性が高いです。
休憩は何を休ませるかを理解する
休憩をとる目的は、脳だけでなく心や体も休めることです。
脳は視覚や聴覚などの感覚器官から入ってくる情報を処理する器官です。
勉強中は特に視覚や聴覚に刺激が多く入ってきます。
そのため、休憩中はこれらの感覚器官からの刺激を減らすことが重要です。
また、心は感情や気分に影響されます。
勉強中は難しい問題やわからない内容にぶつかったり、自分の成績や目標にプレッシャーを感じたりすることがあります。
そのため、休憩中は心のストレスを解消することが重要です。
それから、体は姿勢や動作に影響されます。
勉強中は座ったままの姿勢が長く続くため、休憩中は体の血流や筋肉を改善することが重要です。
休憩をとるときに気を付けたいこと
休憩をとることは勉強の効率を上げるために必要ですが、休憩の方法や時間によっては逆効果になることもあります。
休憩をとるときに気を付けたいことは以下の通りです。
休憩時間は15分以下か30分以上のどちらかにする。
(休憩が不十分もしくは休憩のし過ぎになる)
休憩中は勉強に関係することはしない。
(休憩中に勉強に関係することをすると、脳や心が休まらず、ストレスがたまりやすい)
休憩後はすぐに勉強に戻る。
(休憩の効果が失われてしまう)
上記の点に気を付けて勉強中の休憩を取る必要があります。
次章では休憩時間の目安をご紹介します。
最適な休憩時間の目安

次は最適な休憩時間の目安をご紹介します。
より実践的な内容ですので、ぜひ実行してみてください。
人間の集中力の限界を知る
まずは自分の集中力の限界を知ることが重要です。
人間の集中力は一定ではなく、時間や状況によって変化します。
先述のとおり、一般的には、大人でも45分程度が集中できる平均時間と言われています。
しかし、集中力の持続は人それぞれですので、自分自身がどこまで集中できるかを把握する必要があります。
集中力が切れた状態で勉強を続けても、脳は情報を十分に吸収できません。
また、疲労やストレスがたまり、勉強への興味や意欲が低下してしまいます。
したがって、自分の集中力が切れそうになったら、無理に勉強を続けるのではなく、休憩をとることが賢明です。
休憩なしで勉強することは非効率であり、逆効果になる可能性が高いです。
自分の集中力の限界を知り、それに合わせて休憩をとることで、勉強の効率を上げることができます。
25分勉強して5分休む「ポモドーロ法」を利用する
ポモドーロ法は短時間の勉強と短い休憩を繰り返すことで、脳の疲労を回復させ、集中力を高めることができる方法です。
具体的には以下のように勉強と休憩を繰り返します。
①25分勉強する→5分休む
②50分勉強する→10分休む
③75分勉強する→15分休む
また、この方法のメリットは以下の通りです。
25分という短い時間ならば、気力や体力を使い切ることなく集中できます。
5分という短い休憩ならば、気が散ることなく勉強に戻れます。
25分間の勉強を1回のサイクルとしてカウントすることで、自分の進捗や成果を可視化できます。
タイマーを使って時間を管理することで、無駄な時間や遅延を防げます。
ただし、この方法を取り入れるには、以下の準備が必要です。
スマートフォンなどのタイマー機能を持ったデバイス
勉強する内容や目標を紙やノートに書き出す
勉強する場所や時間帯を決める
勉強中に邪魔になるものや人を避ける
準備を万全にしてポモドーロ法を活用してください。
学校の授業時間と休み時間のサイクルを採用する
学校では一般的に50分間の授業後に10分間の休み時間が設けられていることから考えられた方法です。
学校での授業に慣れている人にとっては、自然なサイクルで勉強と休憩を繰り返すことができます。
具体的には次のサイクルで勉強と休憩を繰り返します。
①50分勉強する→10分休む
②100分勉強する→20分休む
③150分勉強する→30分休む
この方法のメリットは以下の通りです。
50分という時間は、集中力が持続する平均時間に近いため、効果的な学習ができます。
10分という休憩は、脳や体に十分な回復効果を与えるだけでなく、次の科目への切り替えもしやすくなります。
100分や150分という長時間の勉強は、集中力の持続力や忍耐力を鍛えることができます。
学校での授業時間と同じサイクルならば、学校の勉強と自宅の勉強の一貫性が保たれます。
この方法を取り入れるには、以下の準備が必要です。
学校の時間割や科目を参考にして、自分の勉強計画を作る
タイマーを使って時間を管理する
休憩中は目や耳などの感覚器官を休める
長時間の勉強後は、仮眠や食事などで深いリラックス効果を得る
ポモドーロ法よりも勉強時間が長くなる場合もあるので、上手く組み合わせて実行してみましょう。
志望校の試験時間のサイクルにあわせる
受験生が受ける予定の試験の時間割や休憩時間を参考にして、勉強と休憩のサイクルを決める方法です。
実際の試験に近い状況で勉強することで、試験対策や慣れの効果を高めることができます。
具体的には次の方法で実践します。
①志望校の試験時間割を調べる
②各科目の試験時間と休憩時間を確認する
③そのサイクルに合わせて勉強と休憩を繰り返す
この方法のメリットは以下の通りです。
試験時間に合わせて勉強することで、試験範囲や問題数に対する感覚やペース配分が身につきます。
休憩時間に合わせて休むことで、試験中に必要な体力や気力のコントロールができます。
試験当日になっても、慣れたサイクルで臨むことができるので、緊張やパニックを防ぐことができます。
試験時間割に沿って勉強することで、自分の志望校への意識やモチベーションが高まります。
この方法を取り入れるには、以下の準備が必要です。
志望校の試験情報や過去問を入手する
試験時間割に沿った勉強計画を作成する
タイマーを使って時間を管理する
休憩中は軽く体を動かしたり水分補給したりする
こちらも勉強時間が長くなる傾向にあるため、ポモドーロ法で慣れてから実践しても良いでしょう。
勉強は長時間続けるよりも、適度な休憩をはさむ方が効率的です。
自分に合った休憩方法や時間を見つけて、質の高い学習を実現しましょう。
長い休憩も交ぜるとさらに勉強効率アップ
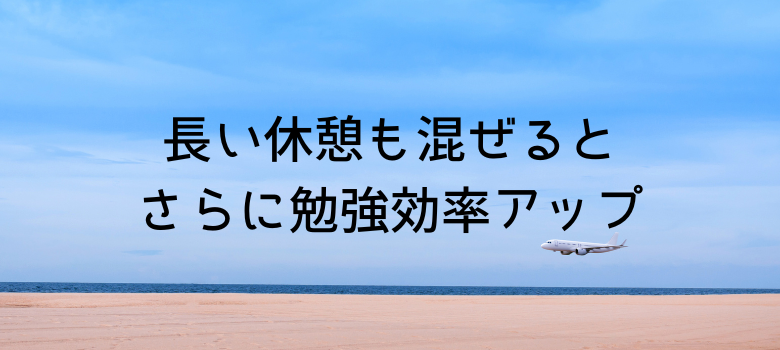
勉強は短時間の休憩だけではなく、長い休憩も必要です。
長い休憩をとることで、脳や体の深い疲労を回復させ、勉強の効率や成果を高めることができます。
では、どのように長い休憩をとればよいのでしょうか?ここでは、長い休憩の方法と注意点について解説します。
1時間以上のロング休憩方法もおすすめ
1日の勉強時間が長くなる場合は、10分程度の短い休憩だけでは不十分です。
そんなときは、思い切って1時間以上の長い休憩をとってしまいましょう。
1時間以上のまとまった休憩をとれば、自分が最もリフレッシュしやすい方法で頭や体を休められます。
例えば、以下のような方法がおすすめです。
散歩やジョギングなどの運動をする
運動は血流や代謝を促進し、脳に酸素や栄養を送り込むことで、脳の活性化や記憶力の向上に効果的です。
趣味や好きなことに没頭する
趣味や好きなことはストレスを解消し、気分を明るくすることで、勉強へのモチベーションや集中力を高めることができます。
友達や家族と話す
友達や家族と話すことは、孤独感や不安感を和らげ、支えや励ましを得ることができます。
また、会話は脳の言語能力や思考力を刺激することで、勉強にも役立ちます。
長時間の休憩は単に睡眠を取る以外の方法もありますので、実践してみてください。
長い昼寝は要注意
昼寝は脳や体にリラックス効果を与えることで、勉強の効率を上げることができます。
しかし、昼寝の時間が長すぎると逆効果になる場合があります。
例えば、以下のようなデメリットがあります。
昼寝が長すぎると夜眠れなくなる
昼寝は睡眠リズムに影響するため、昼寝が長すぎると夜に入眠障害や睡眠不足を引き起こす可能性があります。
昼寝が長すぎると頭がぼーっとする
昼寝は睡眠サイクルに影響するため、昼寝が長すぎると深い睡眠に入ってしまい、起きた後に頭がぼーっとしたり眠気が残ったりする現象が起こります。
昼寝が長すぎると勉強のリズムが崩れる
昼寝は気分転換にもなりますが、昼寝が長すぎると勉強から離れすぎてしまい、再開する際に集中力やモチベーションが低下する可能性があります。
以上のことから、昼寝をする場合は15分から30分程度に抑えることがおすすめです。
また、昼寝の前にコーヒーを飲んだり、昼寝の後に水を飲んだりすることで、眠気をさますことができます。
勉強は短時間の休憩だけではなく、長い休憩も必要です。
長い休憩をとることで、脳や体の深い疲労を回復させ、勉強の効率や成果を高めることができます。
しかし、長い休憩も適切な方法や時間に注意することが大切です。
勉強効率が上がる休憩の過ごし方
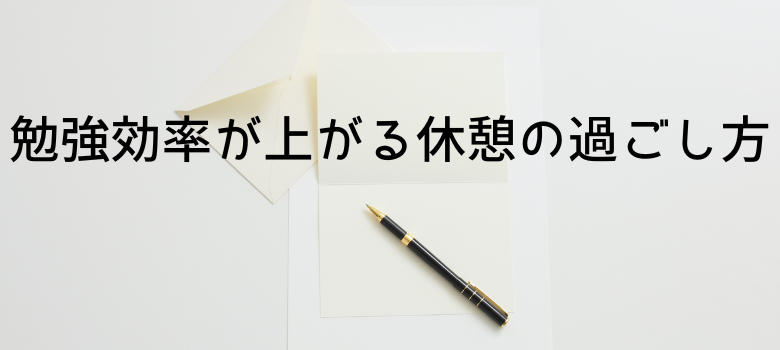
ここからは勉強効率が上がる休憩の過ごし方をご紹介します。
休憩中の過ごし方に困ったときの参考にしてください。
軽度の運動
休憩時間中に軽度の運動をすることは、血流や代謝を促進し、脳に酸素や栄養を送り込むことで、脳の活性化や記憶力の向上に効果的です。
また、運動はストレスホルモンの分泌を抑え、気分を明るくすることで、勉強へのモチベーションや集中力を高めることができます。
軽度の運動としては、以下のようなものがおすすめです。
ストレッチやラジオ体操などの柔軟体操
腕立て伏せやスクワットなどの筋力トレーニング
散歩やジョギングなどの有酸素運動
ヨガやピラティスなどのバランストレーニング
これらの運動は、自宅でも簡単にできるものばかりです。
休憩時間中に5分から10分程度行うだけで十分な効果が得られます。
ただし、運動する際は以下の点に注意してください。
運動前後に水分補給をする
運動後に息切れしない程度にする
運動後に汗を拭き取る
運動後に少し休んでから勉強に戻る
過度な運動にならないように注意しながら取り組んでみてください。
仮眠
仮眠(昼寝)は脳や体にリラックス効果を与えることで、勉強の効率を上げることができます。
例えば、以下のようなメリットがあります。
脳の疲労を回復させ、集中力やモチベーションを高めることができます。
短時間の睡眠でも、記憶力や理解力が向上する効果があります。
ストレスホルモンの分泌を抑え、気分を明るくすることができます。
ストレスの蓄積を予防し、心に余裕ができます。
睡眠負債の解消方法としても期待されています。
睡眠負債とは日々の慢性的な寝不足のことで、さまざまな健康問題の要因となります。
仮眠や昼寝で睡眠不足を軽減することで、体内時計を整え、免疫機能や腸内環境をサポートすることができます。
なお、午後2時から4時の間に仮眠や昼寝をすることがおすすめです。
15時以降は眠気は我慢するようにしましょう。
音楽を聴く
音楽にはさまざまな効果があります。
例えば、好きな音楽を聴くと「ドーパミン」が分泌され、意欲がわきやすくなります。
また、ゆったりした音楽にはリラックス効果が期待できます。
気分をリフレッシュしたり疲れをとったりして勉強を再開したいときは、気分に合う音楽を聴くことで、意識的に気持ちのコントロールが可能になるのです。
音楽を聴く際は以下の点に注意してください。
音量は適度にする
歌詞のある音楽は避ける
勉強中に音楽を聴くのはNG
勉強に集中するためには、BGM程度の音楽がおすすめです。
おやつや水分補給をする
脳の栄養となるブドウ糖は、基本的に体にためておくことができません。
勉強の休憩時間には甘いものなどを少し食べて、使ったエネルギーを頭に補充してあげましょう。
また、休憩中は意識的に水分を補給しましょう。
さまざまな研究から勉強などの知的作業前に0.5リットルの水を飲むことで、パフォーマンスが大きく向上することが判明しました。
ただし、おやつや水分補給をする際は以下の点に注意してください。
甘いものは過度に摂らない
カフェインやアルコールは避ける
食べ過ぎないようにする
上記の行為は勉強の効率を下げるため、水分や食事の摂取には気をつけましょう。
目を閉じて静かに過ごす
目を閉じて静かに過ごすことで、視覚刺激を遮断し、脳の疲労を回復させることができる方法です。
目を閉じると、脳はアルファ波というリラックスした状態の波を出し始めます。
アルファ波は、集中力や創造力を高める効果があると言われています。
ただし、目を閉じて静かに過ごす際は以下の点に注意してください。
周囲の音や光をできるだけ遮断する
深呼吸や瞑想などで心を落ち着かせる
睡眠に入らないようにする
あくまでも目を閉じるだけであって、睡眠に入ると休憩のし過ぎになる可能性があります。
休憩中のスマホはNG
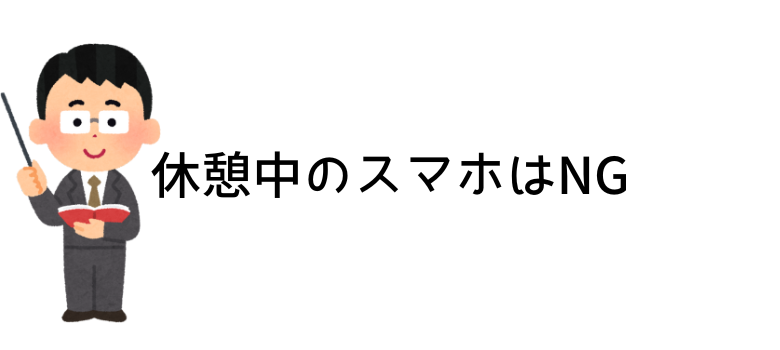
休憩中はスマホ操作を控えましょう。
スマホは脳を休ませないからです。
スマホ操作について、勉強に対するデメリットを解説します。
スマホは脳を休ませない
スマホにはさまざまな情報や刺激が溢れています。
SNSやゲーム、ニュースや動画など、気になるものがたくさんあります。
しかし、それらに目を向けることで、脳はさらに疲れてしまうわけです。
スマホを見ることで、脳は以下のような影響を受けます。
視覚的な情報を処理することで、脳はエネルギーを消費します。
スマホの画面から出る青色光は、メラトニンという睡眠ホルモンの分泌を抑えます。
スマホの操作によって、ドーパミンという快楽物質が分泌されます。
スマホの通知音や振動は、注意力を散漫にします。
これらの影響によって、スマホを見た後は眠気や倦怠感が残り、勉強に集中しにくくなります。
また、スマホに夢中になりすぎて、休憩時間が長くなってしまうこともあります。
これでは、休憩の意味がありません。
難関大学や医学部の合格者は仮眠一択?
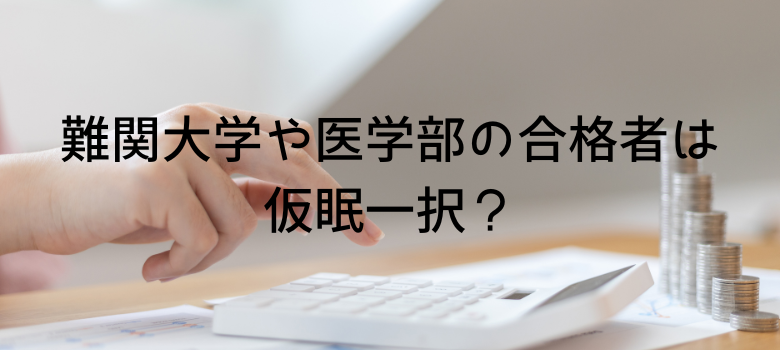
難関大学や医学部の合格者は勉強の合間に仮眠をとる傾向があります。
仮眠をとることで、勉強の効率や成績を向上させているというケースもあります。
ただし、仮眠をとらない人も少なくありませんでした。
仮眠が合わない人や、仮眠をとると夜眠れなくなる人もいるからです。
仮眠は一択ではありませんが、自分に合った方法で取り入れることで、勉強のパフォーマンスを高めることができます。
これらはあくまでも一例であり、個人差もあります。
自分に合った仮眠の方法を見つけて、勉強効率をアップしましょう。
まとめ
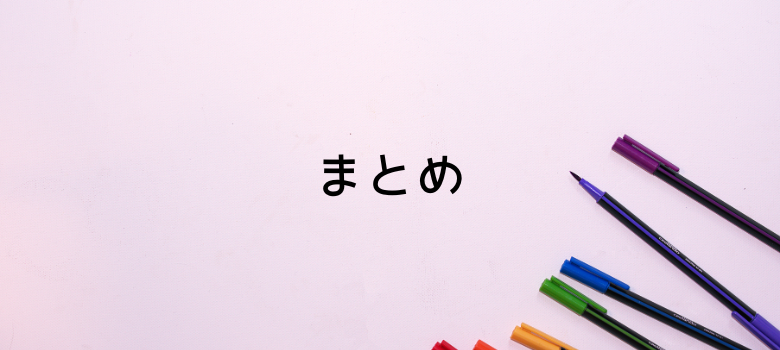
この記事では、勉強効率が上がる休憩の過ごし方について解説しました。
休憩は脳の疲労を回復させるだけでなく、記憶の整理や定着、創造性や問題解決能力の向上にも役立ちます。
しかし、休憩の時間やタイミングが不適切だと逆効果になる場合があります。
ぜひ、記事の内容を参考にして、質の高い休憩をとってください。
この記事の執筆者:医進の会代表 谷本秀樹

大学入試は四谷学院などの大手予備校や多くの医学部受験予備校で、主に生物の集団授業と個別授業で300人以上の受験生を担当。
自身の予備校『医進の会』発足後は、これまで500人以上の生徒の受験と進路指導に携わってきた。
圧倒的な医学部入試情報量と経験値、最適なアドバイスで数多くの受験生を医学部合格に導いてきた、医学部予備校界屈指のカリスマ塾長。

