帝京大学医学部の偏差値や学費、入試情報は?入試傾向や対策方法、奨学金や倍率も解説
- 公開日
- 更新日
カテゴリ:大学情報

帝京大学医学部は東京都板橋区に所在する私立大学です。
本記事では、帝京大学医学部の入試情報や合格難易度、奨学金制度についてまとめています。
また、科目別の入試傾向と対策方法についても詳しく解説しているので、帝京大学医学部の受験を考えている方や医学部に興味のある方は是非参考にしてください。
帝京大学医学部の基本情報

まずは帝京大学医学部の基本情報をまとめてみました。
帝京大学医学部の定員・生徒数・住所
| 入学定員 | 118名 |
|---|---|
| 生徒数 | 760名 |
| 収容定員 | 702名 |
※2024年5月のデータです。
医学部の定員は118名です。
6学年合わせた生徒数は760名となっています。
| キャンパス | 板橋キャンパス |
|---|---|
| 住所 | 〒173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1 |
| アクセス | ・「JR十条駅」より徒歩約10分 ・JR京浜東北線「王子駅」下車 国際興業バス6番のりば→板橋駅行10分「帝京大学病院」下車 国際興業バス7番乗り場→赤羽駅西口行15分「帝京大学病院正面」下車 |
帝京大学医学部は板橋キャンパスに属しています。
アクセスは十条駅から徒歩約10分または、王子駅からバスに乗換え大学の目の前に到着します。
どちらの行き方もアクセスは良いです。
帝京大学医学部の入試情報
続いて帝京大学医学部の入試情報をまとめてみました。
入試日程や合格最低点
| 日程方式 | 入試日程 |
|---|---|
| 学校推薦型 | 2024年11月17日(日) |
| 一般選抜 特別地域枠* |
【一次選考】2025年1月23日(木)、24日(金)、25日(土) 【二次選考】2025年2月6日(木)、7日(金) ※どちらか1日 |
| 共通テスト利用選抜 | 【前期:一次選考】大学共通テスト 【前期:二次選考】2024年2月16日(金) |
特別地域枠は、福島県、千葉県、静岡県、茨城県、新潟県の5県です。
【2024年度の合格最低点】
| 入試区分 | 配点 | 合格最低点 |
|---|---|---|
| 学校推薦選型選抜 | 300 | 187 |
| 一般選抜 | 300 | 217 |
| 一般選抜(福島枠) | 300 | 185 |
| 一般選抜(千葉枠) | 300 | 175 |
| 一般選抜(静岡枠) | 300 | 216 |
| 一般選抜(茨城枠) | 300 | 196 |
| 一般選抜(新潟枠) | 300 | 197 |
| 共通テスト利用 | 600 | 444 |
共通テスト・二次試験の配点
共通テスト利用選抜の一次選考は、共通テストにおいて指定された教科・科目の成績により高得点3科目の合計で合否を判定します。
一次選考の合格者は、二次選考で英語(長文読解)試験と課題作文試験と面接を行います。
3科目方式
| 教科 | 科目 | 選択 | 配点 | 個別学力検査等 |
| 外国語 | 英語 | 必須 | 各科目100点合計300点満点(1次選考) | 英語(長文読解)課題作文面接(一次選考合格者に限る) |
| 数学 | 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | 2科目選択 | ||
| 理科 | 「物理」「化学」「生物」 | |||
| 国語 | 「国語」 |
5科目方式
| 教科 | 科目 | 選択 | 配点 | 個別学力検査等 |
|---|---|---|---|---|
| 外国語 | 英語 | 必須 | 各科目100点合計500点満点(1次選考) | 英語(長文読解)課題作文面接(一次選考合格者に限る) |
| 国語 | 「国語」 | |||
| 数学 | 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ、数学A」「数学Ⅱ、数学B、数学C」 | 3科目選択 | ||
| 理科 | 「物理」「化学」「生物」 |
大学入学共通テスト利用選抜は、3科目方式への出願を必須とし、追加で5科目方式を出願することができます。
二次試験は一次選考合格者に限り、本学独自の英語(長文読解)の試験と課題作文の試験、面接を行い、合否を判定します。面接は受験者1名に対し教員2名で10分程度行います。
帝京大学医学部の学費・奨学金

帝京大学医学部の学費・奨学金についてまとめました。
学費・授業料
| 1年次 | 入学金 | 1,050,000円 |
|---|---|---|
| 授業料 | 3,150,000円 | |
| 施設拡充費 | 2,100,000円 | |
| 教育維持費 | 2,835,000円 | |
| 実験実習費 | 227,000円 | |
| 学生傷害保険費 | 8,140円 | |
| 初年度納入金総額 | 9,370,140円 | |
| 2年次以降の年額 | 6,002,000円 | |
| 6年間の総額 | 39,380,140円 | |
帝京大学医学部の6年間の学費の総額は、39,380,140円です。
私立大学医学部の学費は約20,000,000~30,000,000円台前半であることが多いため、帝京大学医学部の学費は比較的高いといえます。
奨学金
帝京大学医学部で利用できる奨学金についてまとめました。
| 名称 | 対象者 |
| “自分流”奨学金制度 | 入学後、家計支持者の死亡、失職等が原因で家計状況が急変し、経済的に修学が困難となった学生。 |
| 福島県地域医療医師確保修学資金 | 帝京大学医学部一般選抜(福島県特別入試枠)で入学し、在学中は福島県が定める「キャリア形成卒前支援プラン」、卒業後は福島県が定める「キャリア形成プログラム」の適用を受け、福島県が指定する医療機関に医師として勤務することを誓約できる者。 |
| 千葉県医師修学資金貸付制度 | 帝京大学医学部一般選抜(千葉県特別地域枠)で入学し、在学中は千葉県が定める「キャリア形成卒前支援プラン」、卒業後は千葉県が定める「キャリア形成プログラム」の適用を受け、千葉県知事が指定する医療機関で医師の業務に従事することを誓約できる者。 |
| 茨城県地域医療医師修学資金貸与制度 | 本学入学試験前に茨城県へ修学資金貸与の申込をし、かつ県の実施するe-ラーニングを受講したものであって、帝京大学医学部一般選抜(茨城県特別地域枠)で入学し、在学中は茨城県が定める「キャリア形成卒前支援プラン」、卒業後は茨城県が定める「キャリア形成プログラム」の適用を受け、茨城県が指定する医療機関に医師として従事することを誓約できる者。 |
| 静岡県医学修学研修資金 | 帝京大学医学部一般選抜(静岡県特別地域枠)で入学し、在学中は静岡県が定める「キャリア形成卒前支援プラン」、卒業後は静岡県が定める「キャリア形成プログラム」の適用を受け、静岡県がしている医療機関に医師として従事することを誓約できる者。 |
| 新潟県医師養成修学資金貸与制度重点コース | 本学医学部一般選抜(新潟県特別地域枠)で入学し、在学中は新潟県が定める「キャリア形成卒前支援プラン」、卒業後は新潟県が定める「キャリア形成プログラム」の適用を受け、新潟県が指定する医療機関で医師の業務に従事することを誓約できる者。 |
| 帝京大学地域医療医師確保奨学金 | 福島県、千葉県、茨城県、静岡県、新潟県(本学と連携している都道府県)の医師修学資金を申請し、本学を卒業後、県が指定する医療機関に指定された期間を勤務する意思のある者、または本学医学部附属病院分院に指定された期間を勤務する意思のある者。なおかつ高等学校もしくは中等教育学校を2024年3月または2025年3月に卒業した者で、成績優秀にして、かつ心身健全であること。 |
| 帝京大学公衆衛生学研究医養成奨学金 | 帝京大学医学部・大学院医学研究科一貫プログラムによる公衆衛生学研究医養成コースに登録し、公衆衛生学研究医養成コースとして設定した教育活動に参加する意思がある者。なお、この教育活動へは医学部第1学年から参加でき、途中学年からの参加の参加も可能である。医学部卒業後、帝京大学院医学研究科医学専攻に進学して公衆衛生学に関する研究で博士(医学)の学位を取得し、大学院修了後、定められた期間において、公衆衛生学に関する研究に従事する意思がある者。さらに成績優秀にして、心身健全である者。 |
| 帝京大学医学部海外臨床実習奨学金 | 医学部6年生(選考は5年次) |
医学部は基本的に地域医療に携わる意志のある学生に対して手厚いサポートがあります。
上記以外にも、日本学生支援機構による奨学金や地方公共団体・民間育英団体による奨学金を活用することが可能です。
帝京大学医学部の難易度・偏差値
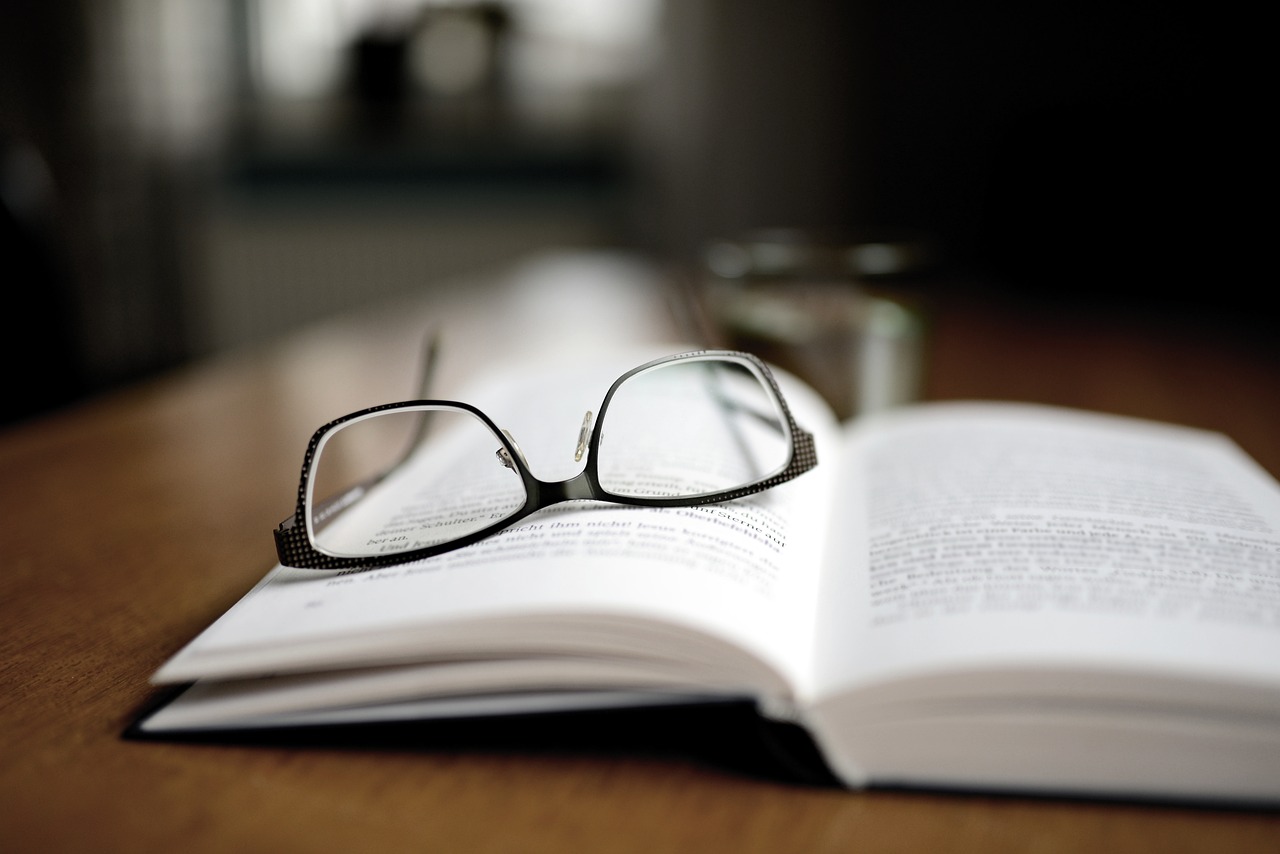
帝京大学医学部の偏差値は 65.0 と言われています。
過去数年の推移を見ても、64~66ほどとなっています。
帝京大学医学部を他の医学部と比較すると?
帝京大学医学部について、偏差値をもとに他大学の医学部と比較してみましょう。
帝京大学医学部の偏差値は、全国82校中52位です。
| 偏差値 | 大学名(一部抜粋) |
|---|---|
| 67.5 | 東邦大学、東京医科大学、東北大学、横浜市立大学、名古屋大学、京都府立医科大学 |
| 65.0 | 帝京大学、山口大学、藤田医科大学、島根大学、日本大学、杏林大学、東北医科薬科大学 |
| 62.5 | 鹿児島大学、和歌山医科大学、富山大学、弘前大学、札幌医科大学、鳥取大学、香川大学、徳島大学、高知大学、大分大学、愛知医科大学 |
医学部全体でみると平均より偏差値は低く、比較的合格を狙いやすいと言えるでしょう。
平均よりは低いですが、帝京大学医学部より上位はほとんどが国公立大学で占められており、私立大学に限定して考えた場合、そこまでレベルが低いというわけではありません。
帝京大学医学部の入試傾向と対策

ここでは、帝京大学医学部の入試傾向と対策についてまとめました。
英語の傾向と対策
大問数は4題で、試験時間は60分です。
解答形式は選択式と記述式です。
読解問題のテーマは、医学的なものか科学的なものが大半で、英米の新聞や雑誌からの出題が多くなっています。
また、単語はレベルの高いものも出題されております。
大問1では、単語の空所補充や内容の真偽、語句の整序及び内容の説明が多く、単語のアクセントを問われることもあります。
また、英文和訳や、指示語の内容説明などの記述式問題も出題されています。
2024年度は英文和訳に字数制限がつき、そのほかの読解問題は、空所補充や与えられた英文の続きを選ぶ形式の内容説明、本文の内容を踏まえた上での語句整序など、多彩な設問が出題されています。
大問1は内容、語彙ともにレベルが高いため、文章の論理的な展開をつかむのが難しいかもしれません。
筆者の意図を正確に把握して、空所を補いながら読まなければならない場面もあります。
そのほかの大問のレベルは標準的といえますが、判断に迷う問題もあるため、高いレベルの英語力は必要です。
英語の対策としては、論理展開と主題を正確に掴み、筆者の主張を捉えることが重要です。
そのために、文法や構文をしっかり押さえておきましょう。
和訳する問題もあるため、ただ長文を読んで理解するだけでなく、文章の一部を日本語に訳し記述する練習もしておきましょう。
また、医学・科学・健康がテーマの長文を数多くこなし、慣れておくことも必要です。
また、新聞や雑誌などで最新の科学記事を読むことも有効でしょう。
長文読解においても文法と語彙力がポイントとなります。
辞書で調べる際は、メインの意味だけでなく、イディオムや用例、発音、派生語にも目を通す習慣をつけましょう。
また、単語の語源を知っておくことで、意味を覚えるのに有利なことがよくあります。
したがって、辞書も語源記事があるものがよいでしょう。
熟語・語句整序問題の対策としては標準的な問題集を1冊繰り返し解きましょう。
発音やアクセントは頻出語を中心にチェックしておきましょう。
文法力をつけるには、受験生が間違いやすいポイントを網羅した総合英文法書などを手元に置きながら学習を進めましょう。
さらに、問題集や過去問を解き、さまざまな設問形式に慣れておきましょう。
また、近年は出題されていませんが、基礎レベルの会話表現の応答はマスターしておきましょう。
数学の傾向と対策
大問数は4題で、試験時間は2科目120分です。
解答形式は2023年度までは空所補充形式でしたが、2024年度は大問4で図示問題が出題され、空欄に符号や数字などを入れるマークシート方式となりました。
出題範囲は「数学Ⅰ・Ⅱ・A(図形の性質、場合の数と確率)・B(数列)・C(ベクトル)」です。
大問4題でそれぞれが2~4問の小問に分かれています。
よく出る範囲は微分・積分法で、そのほか、場合の数と確率、三角関数、整数の性質、指数・対数関数、数列、ベクトルなど、各分野から満遍なく出題されています。
また、いくつかの単元をまたぐ融合問題の出題もあります。
標準レベルの問題が中心ですが、骨がある問題も出題されているため、計算力・思考力ともに必要となるでしょう。
数学の対策としては、教科書のレベルの学習をし、公式や定理などの基本事項を身につけ、基礎力をつけることが大切です。
三角関数や指数・対数関数、ベクトルの公式や数列の和の計算といった、教科書に載っている公式に加えて、やや高度な考え方を含む解法も利用することで、速く簡単に処理できる問題もあります。
いろいろな公式や定理を身につけ、標準レベルの問題や典型的な問題からやや難しい問題まで解けるようにしておきましょう。
教科書の学習だけでは合格点に達するのは厳しいため、標準~やや難レベルの問題集で実戦演習をしておきましょう。
また、解法パターンに当てはめるだけでは解けない応用問題も出題されることがあります。
どうしてその解法で答えが求められるのかを考え、理解することで、発想力を鍛えましょう。
大部分が結果のみを記入する空所補充形式のため、計算ミスをしないように気を付けましょう。
普段から速く正確な計算を行う習慣をつけ、解答中は検算や見直しを行いながら解き、計算ミスを減らしましょう。
化学の傾向と対策
大問数は4題で、試験時間は2科目120分です。
解答形式は選択式と記述式ですが、2024年度は選択式においてマークシート方式が採用されました。計算問題は結果のみの解答であり、途中の計算式は求められていません。
出題範囲は「化学基礎・化学」です。
小問集合形式の問題が多く、理論・有機・無機分野がバランスよく出題されています。
また、医学に関連して、アミノ酸や、タンパク質、脂質といった天然高分子化合物からの出題もよくみられます。
基礎から標準レベルの問題を中心に、難問や細かい知識を問う問題も出題されています。
選択問題は、一見すると易しいように思えますが、選択肢のすべてが当てはまるものや該当するものがない場合もあり、正確な知識が求められます。
また、計算問題では、有効数字の桁数や表記法に細かい指示があるため、慎重な解答が必要です。
試験時間と出題数を考慮すると、1題あたり約15分で解くことになるでしょう。
化学の対策としては、理論分野のアンモニアの電離平衡や酢酸は、緩衝液や加水分解平衡まで含めて応用問題対策をしておきましょう。
平衡移動からの出題は多いですが、易しい問題です。
気体の法則では、蒸気圧を含めた混合気体の燃焼など、やや難しい問題への対策が必要でしょう。
希薄溶液からの出題では、沸点上昇と凝固点降下、また浸透圧について、揮発性・不揮発性、非電解質・電解質に着目して計算に当たりましょう。
金属イオンの分離と検出では実験操作を含めて詳細も含めて理解しておきましょう。
基本から標準レベルの設問となっているため、得点源としたい分野です。
時間をかけずに解きましょう。
また、資料集を利用し、グラフや表を参考にして理解を深めましょう。
有機分野では天然高分子化合物の性質や計算に関する出題が多いため、アミノ酸・タンパク質、油脂、糖類、天然ゴムなどの項目は、しっかり学習しておきましょう。
その際、教科書に記載されている物質を中心にまとめておくとよいでしょう。
有機化合物の構造決定については、組成式・分子量から分子式を求め、物質の性質や検出反応(銀鏡反応、加水分解反応など)を通して構造を決めるもので、どの問題集でもみられる問題といえるでしょう。
物理の傾向と対策
大問数は3題で、試験時間は120分です。
2023年度までは答えのみを記入する形式で、空所補充形式の問題も出題されていましたが、2024年度は答えのみを記入する形式と、マークシート方式による選択式が混在していました。マークシート方式は、選択肢番号をマークするものと、解答の数字そのものをマークするものが出題されています。
出題範囲は「物理基礎・物理」です。
全分野から満遍なく出題されていますが、必出は力学で、次いで電磁気がよく出題されています。
また原子分野からの出題もみられます。
文字式の計算といった計算問題も多く出題されています。
論述・描図問題の出題は過去にはありません。
難易度は全体を通して基本から標準レベルで、無理なく解ける問題が大半を占めますが、なかにはやや難度が高い問題もみられます。
物理の対策としては、教科書を隅々まで読み、設問や例題を解きつつ基本事項をしっかり理解しましょう。
また、受験参考書も活用し、重要な法則や原理、および重要公式の導出過程などをノートにまとめることも有効です。
基礎レベルから教科書の章末問題レベルの問題が中心のため、教科書傍用問題集で応用力や計算力をつけましょう。
物理の問題を解く上では、図を描いて内容を整理し、考える習慣を身につけましょう。
教科書の図やグラフにも入念に目を通しましょう。
出題の傾向や形式に慣れるために、過去問の演習をすることをおすすめします。
その際は、よく出題されている法則・公式などを確認しましょう。
また、数値計算の問題は必ず自分で計算し、有効数字の扱いもマスターしておきましょう。
生物の傾向と対策
大問数は3題で試験時間は2科目120分、解答形式は2024年度は選択式がマークシート方式となり、マークシート方式による選択問題と論述問題のみの出題でした。
出題範囲は「生物基礎・生物」です。
体内環境からは毎年出題されており、遺伝情報や代謝からも多く出題されています。
頻出分野があるものの出題頻度の少ない分野が大問題で取り上げられる年度もあり、総合問題も見られますので、全出題範囲を偏りなく学習するようにしましょう。
過去には免疫、細胞について腎臓に関しての詳しい知識を必要とする出題もあり、短い論述問題が出題された年度もあります。
標準的な問題が中心ですがやや難しい問題も出題されています。
先ずは教科書の基礎知識を充実させることが大切です。
標準レベルの問題集を繰り返し学習し、曖昧な箇所は資料集で確認し、知識を定着させましょう。
生物用語は正しく記述できるよう心がけ、また20~30字程度の論述問題も出来るようにしておきましょう。
教科書は隅々まで目を通し、細かい数値などにも注意を払いましょう。
また早い段階で過去問に挑戦して苦手分野の把握、時間配分の感覚を身につけることも重要です。
苦手分野は繰り返し練習するなどして克服しておきましょう。
国語の傾向と対策
大問数は3題で試験時間は2科目120分、解答形式は記述式・選択式が併用されていますが、2024年度は選択式でマークシート方式が採用され、記述式は字数指定のある内容説明のみでした。
評論中心の出題で、テーマは文学・言語・思想・科学論等です。
翻訳された文章の出題が目立ち、設問内容は多彩ですが特に空所補充問題が多く読解はやや難しいでしょう。
語句の意味や細部の表現、指示語の内容や接続詞の働きなど的確に把握して、文や段落相互の関係を押さえた上で、各段落の要旨から全文の論旨・主題を理解するよう努めましょう。
記述式と選択式問題のどちらにも対応できる問題を集めた基礎的な問題集に取り組み、四字熟語や慣用表現、ことわざなども出題されることがありますので、これらも覚えておきましょう。
また手間取る設問があると時間が足りなくなってしまう可能性もありますので、過去問を利用し時間配分の対策もしておく必要があります。
じっくり読みこんで時間をかける解き方と素早く解く解き方のどちらの練習もしておきましょう。
帝京大学医学部に合格するなら医進の会
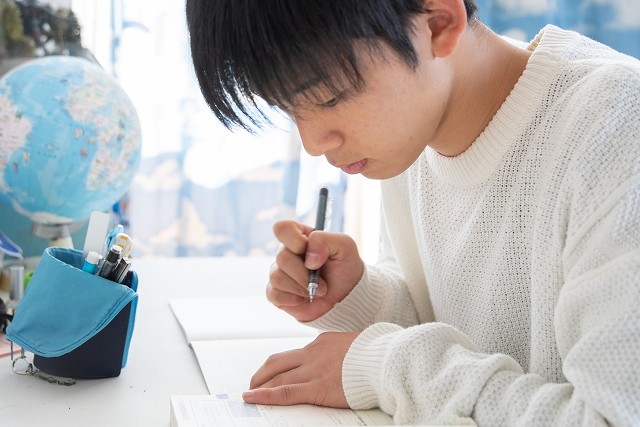
帝京大学医学部は偏差値ランキングも全国52校のうちで51位であり、やや易~標準レベルではありますが、就職実績等の理由で人気があるため倍率は高くなっております。
そのため帝京大学医学部合格を目指すのであれば独学ではなく、塾予備校で学習することをおすすめします。
医進の会ではプロ講師による完全個別指導を行っており、生徒1人1人の学力等に合わせ、生徒の要望に寄り添い個別のカリキュラムを組んでいきます。
教材も生徒個人に合わせたものを使用し、学習内容が定着したかどうかのテストも行い細やかなフォローをしていきます。
また、授業以外の時間にも個別のブースで自習ができ、苦手分野や勉強法を国公立現役医学部生であるチューターへ質問したりすることもできます。
疑問があればすぐに解決できる環境ですので、不安無く受験勉強に集中できる環境が整っております。
さらに希望があれば志望理由書の指導や相談も受け付けており、無料の面接練習も可能です。
無料面談・体験授業も行っておりますので、気になられた方は、是非、お問い合わせください。
医進の会でお待ちしております。
無料の体験授業・面談はこちら無料電話問い合わせ
06-6776-2934
まとめ

今回は帝京大学医学部の基本情報や入試情報などについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
帝京大学医学部の受験を検討中の方は、人気のある大学ですので早い時期から学習計画を確立し、医学部受験予備校への入会も検討しながら受験対策を進めましょう。
また本記事を通して帝京大学医学部に興味を持たれた方は、ぜひ検討してみてください。
公式サイト:帝京大学
この記事の執筆者:医進の会代表 谷本秀樹

大学入試は四谷学院などの大手予備校や多くの医学部受験予備校で、主に生物の集団授業と個別授業で300人以上の受験生を担当。
自身の予備校『医進の会』発足後は、これまで500人以上の生徒の受験と進路指導に携わってきた。
圧倒的な医学部入試情報量と経験値、最適なアドバイスで数多くの受験生を医学部合格に導いてきた、医学部予備校界屈指のカリスマ塾長。

